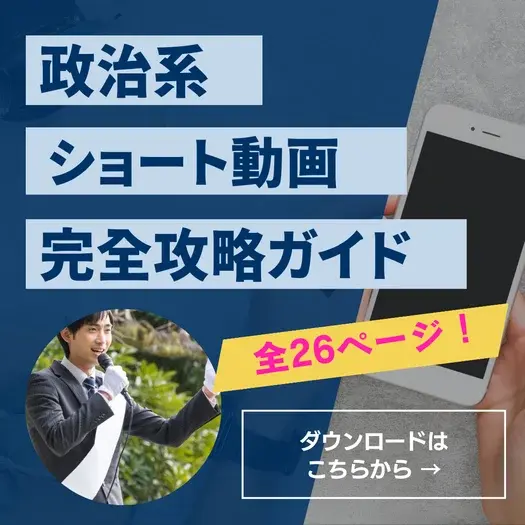目次
はじめに
2025年は、国政選挙をはじめとする複数の重要な選挙が予定されています。とくに参議院議員通常選挙を控えており、立候補を検討している方にとっては、早めの情報収集と準備が欠かせません。
本記事では、2025年に予定されている主な選挙スケジュールを整理するとともに、立候補に向けた手続きや必要な準備について、具体的に解説します。
インターネットの普及により、政治活動のあり方は大きく変わりました。かつては街頭演説や集会、新聞やテレビを通じた発信が中心でしたが、今ではSNSや動画配信、オンラインコミュニティを活用した情報発信が当たり前になっています。誰もが政治に関する意見を広められる時代になった今、政治活動にはどのような変化が起きているのでしょうか。
本記事では、インターネットが政治活動にもたらした影響や、活用のメリット・デメリット、注意すべき点について詳しく解説します。
2025年の選挙スケジュール総まとめ
2025年には、国政選挙である参議院議員通常選挙が予定されているほか、東京都や大阪府をはじめとした地方自治体でも首長選挙や議会議員選挙が行われる見通しです。選挙の実施時期や公示・告示日、投開票日は自治体や選挙の種類によって異なるため、早めに情報を確認しておくことが重要です。
以下では、主要な選挙ごとに想定される日程や概要を整理して紹介します。
参議院議員通常選挙
【日程:7月上旬~中旬に実施見込み(任期満了日:7月28日)】
2025年には、第27回参議院議員通常選挙が予定されています。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに全議席の半数が改選される仕組みです。今回は、定数248のうち124議席が対象となります。
選挙の方式は、選挙区制と比例代表制の2つ。選挙区制では、全国を45の選挙区に分け、定数に応じて74名が選ばれます。一方、比例代表制では全国を1つの単位とし、政党名で投票を行い、50名が選出される形式です。
任期満了日は2025年7月28日と定められています。公職選挙法により、選挙期日はこの日からさかのぼって30日以内に設定されるため、7月上旬〜中旬の実施が見込まれるでしょう。国会の会期や他の政治日程との調整により、正式な日程は今後確定される予定です。
衆議院議員総選挙
【日程:未定(次回任期満了は2028年10月/ただし解散により前倒しの可能性あり)】
衆議院議員の任期は4年と定められていますが、過去の例から解散総選挙が行われることが一般的です。前回の第50回衆議院議員総選挙は、2024年10月27日に実施されました。そのため、次回の総選挙は、通常の任期満了に伴う場合、2028年10月頃に予定されます。
ただし、衆議院は解散権が内閣総理大臣に与えられているため、政治状況により任期満了前に解散総選挙が行われる可能性もあります。
選挙制度は、小選挙区と比例代表の並立制。小選挙区では全国を289の選挙区に分け、各選挙区から1名ずつ計289名が選出されます。比例代表では全国を11のブロックに分け、各ブロックごとに政党名で投票を行い、得票数に応じて計176名が選出されます。
東京都の選挙
【日程】
2025年、東京都内では上記22個の選挙が予定されています。そのなかで最も注目されるのは、東京都議会議員選挙です。この選挙は、6月22日に投票が行われ、127名の都議会議員が選出。告示日は同年6月13日とされています。都議会議員の任期は4年で、前回の選挙は2021年に実施されました。
東京都内で実施される選挙についての詳細および最新情報は「東京都選挙管理委員会 令和7年 選挙執行一覧」をご確認ください。
大阪府の選挙
【日程】
大阪府内でも複数の選挙が予定されています。参議院議員通常選挙では、参議院の全議席の半数が改選されます。大阪府選挙区においては、定数4議席が争われる見込みです。前回の参院選では、大阪府選挙区において日本維新の会が2議席を獲得し、他の主要政党と激しい競争を繰り広げました。今回も各党の戦略や候補者選定が注目されます。
大阪府内で実施される選挙についての詳細および最新情報は「府内の選挙日程及び議員・首長の任期満了日」をご確認ください。
その他の主要地方選挙
【日程】● 横浜市長選挙:未定(2025年8月29日任期満了)● 川崎市長選挙:未定(2025年11月18日任期満了)● 千葉県参議院議員通常選挙:未定(2025年7月28日任期満了)
2025年は、東京都・大阪府以外の地域でも、地方自治体の市区町村長選挙や議会議員選挙が多数予定されています。特に横浜市長選挙は、前回の選挙でIR(統合型リゾート)誘致の是非が大きな争点となり、市民の関心を集めました。IR問題は一応の決着を見たものの、高齢化対策や中学校給食、子育て支援、港湾再開発といった市民生活に直結する課題に対して、今後の市政がどのように舵を切るのかが問われています。
川崎市長選挙においても、人口増加に伴う保育・教育・住宅・インフラ整備など、多くの課題が山積しています。特に格差是正や地域間のバランスある発展が重要なテーマとなっており、次期市長にはこれらの課題解決に向けた具体的なビジョンが求められています。
その他、地方選挙の詳細や最新情報については、各自治体の選挙管理委員会の公式ウェブサイトをご確認ください。

立候補の手順
選挙への立候補には、情熱や政策だけではなく、制度上の理解と入念な準備が欠かせません。初めて選挙に挑む方にとっては、どこから手を付けるべきか迷うこともあるでしょう。
以下では、立候補するために必要な条件の確認や各種の手続き、実務的な準備項目について、順を追って解説していきます。
資格条件の確認
まずは資格条件の確認を行いましょう。選挙に立候補するためには、以下の要件を満たす必要があります。● 衆議院議員:満25歳以上の日本国民● 参議院議員:満30歳以上の日本国民● 都道府県知事:満30歳以上の日本国民● 都道府県議会議員:満25歳以上の日本国民で、当該都道府県の選挙権を有する者● 市区町村長:満25歳以上の日本国民● 市区町村議会議員:満25歳以上の日本国民で、当該市区町村の選挙権を有する者
参照:総務省「立候補を目指す方へ」
これらの要件を満たしているか、立候補を検討する際には事前に確認することが重要です。
政党の公認・推薦の手続き
選挙に立候補する際、政党からの「公認」や「推薦」を受けることで、選挙活動における支援や知名度の向上が期待できます。公認とは、政党が自党の正式な候補者として認めることで、候補者はその党の公認候補として選挙に臨むことになります。公認選挙ポスターや広報物に政党名を掲示でき、報道でも「○○党・氏名」といった形で紹介されます。
一方、「推薦」は、政党が自党の候補者ではないものの、理念や政策が近い無所属の候補者などを支援する際に行われます。推薦を受けた候補者は、選挙公報や投票用紙において「無所属」と記載されますが、政党からの応援や選挙活動の支援を受けることが可能です。
公認や推薦を受けるための手続きに関しては政党ごとに異なりますが、一般的には候補者が所定の申請書類を提出し、党内の選考委員会や総務会での審査を経て決定されます。
手続きの詳細は、各政党の公式ウェブサイトや関連資料を確認してみましょう。
必要書類の準備
立候補を正式に届け出ることが決まったら、該当する選挙の種類や選挙区を明確にし、それに応じた必要書類を準備します。一般的に、立候補届出書、宣誓書、戸籍謄本、住民票、所得税や住民税の納税証明書、供託金の納付証明書などが求められます。これらの書類は、各自治体の選挙管理委員会から提供される指定の様式に基づき作成しなければなりません。
また、選挙公報への掲載を希望する場合は、所定の「選挙公報掲載申請書」や「掲載文原稿」、候補者の写真などの提出も必要です。
書類の提出期限や提出方法も選挙ごとに異なるため、事前に管轄の選挙管理委員会に確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
供託
選挙に立候補するためには、法律で定められた一定の金額を法務局に預ける「供託」が必要です。この制度は、当選を目的としない無責任な立候補を防ぐために設けられています。
供託金の額は選挙の種類によって異なり、例えば衆議院小選挙区選出議員選挙や参議院選挙区選出議員選挙では300万円、都道府県知事選挙でも同じく300万円が必要です。選挙ごとの供託金の額については、「総務省 立候補を目指す方へ」でご確認ください。
● 納付先と納付時期
供託金の納付先は、法務局または地方法務局に設置された供託所と定められています。立候補届出の前に納付を完了させる必要があり、遅れると届出自体が受理されませんので注意が必要です。納付方法は、電子納付または金融機関の窓口での支払いが一般的です。特にペイジー対応のATMやインターネットバンキングを利用すれば、手続きも比較的スムーズに進められるでしょう。
納付手続きが完了すると、供託所から供託書正本が交付されます。この供託書正本は、立候補届出時に選挙管理委員会へ提出する必要があるため、くれぐれも紛失しないよう注意してください。
● 没収条件
選挙に立候補する際に納めた供託金は、得票数が一定の基準に達しなければ没収されます。基準は選挙の種類によって異なります。
例えば、衆議院小選挙区選出議員選挙では有効投票総数の10分の1(10%)未満、参議院選挙区選出議員選挙では有効投票総数をその選挙区の定数で割った数の8分の1(12.5%)未満の得票しか得られなかった場合、供託金が没収されます。
市区町村長選挙や市区町村議会議員選挙でも、それぞれ没収ラインが決まっているので、事前に確認しておきましょう。
届出の手続き
立候補に必要な準備が整ったら、次は選挙管理委員会への届出です。届出手続きは選挙期日の公示日または告示日に行われ、受付時間は曜日を問わず午前8時30分から午後5時までと定められています。うっかり締切を過ぎると受付してもらえないので注意しましょう。
届出方法は選挙の種類によって異なり、例えば衆議院小選挙区選挙では政党、本人、推薦のいずれからでも届出が可能です。一方、参議院選挙区選挙では本人または推薦のいずれかに限られます。
なお、届出の際には、供託証明書、宣誓書、戸籍謄本または抄本など、必要書類を漏れなく提出することが求められます。
事務所や選挙カーの準備
効果的な選挙運動を行うためには、選挙事務所と選挙カーの準備が必要です。選挙事務所は、選挙運動に関する事務を取り扱う場所で、候補者またはその承諾を得た推薦届出者が1カ所設置できます。交通の利便性や有権者が訪れやすい立地を考慮して選定しましょう。
一方、選挙カーは候補者の名前や政策を広く周知する手段として有効です。運行ルートの計画や必要な備品の準備、運動員の心得など、事前にしっかりと準備を進めましょう。
ポスター制作
選挙ポスターは、有権者に候補者の顔と名前を覚えてもらうためのものです。デザインでは、候補者の写真を大きく配置し、名前を明瞭に記載することが求められます。また、キャッチフレーズや政策を簡潔に盛り込むことで、候補者の訴えを効果的に伝えられるでしょう。
ただし、ポスターのサイズや記載内容には公職選挙法による規定があるため、事前に確認が必要です。適切なポスターを作成し、有権者へのアピールにつなげましょう。
スタッフやボランティア集め
選挙活動を一人で完遂することは現実的ではありません。候補者を支える体制づくりとして、スタッフやボランティアの協力が欠かせない場面も多くなるでしょう。支援者の役割は、有権者との接点を築くことから、事務所の運営、ポスター貼りに至るまで多岐にわたります。
以下では、有給で雇用される選挙運動員と無償で参加するボランティアの違いや、それぞれに求められる手続き・注意点について詳しく解説します。
● 有給の選挙運動員
選挙運動では、特定の役割において報酬を受け取る運動員を雇用することが認められています。例えば、車上運動員(いわゆる「ウグイス嬢」や「カラス」)や手話通訳者については、事前に選挙管理委員会へ届出を行えば、法定の上限額内に限り報酬の支払いが可能です。
ただし、上限額を超えて報酬を渡したり、本来は無償で活動すべき運動員に金銭を支払った場合には「買収」とみなされ、公職選挙法違反に問われることになるため注意しなければなりません。実際、2019年の参議院議員選挙では、車上運動員に上限を超える報酬を支払ったとして、関係者が買収罪に問われた事例もありました。
こうした違反が発覚した場合、候補者の当選が無効となるだけでなく、連座制の適用により、一定期間同じ選挙区から立候補することができなくなる可能性も出てきます。したがって、有給の選挙運動員を活用する際は、これらの規定を十分に理解し、法令を遵守することが求められます。
● 無給のボランティア
選挙運動は、基本的にボランティアの力によって成り立っています。ポスターの掲示やビラ配り、イベント運営、有権者への電話での呼びかけなど、候補者ひとりでこなすのは到底不可能です。こうした運動を支える人たちがいてこそ、選挙活動は効果的に展開できるのです。
ただし、選挙運動員への報酬については公職選挙法により厳しく規制されており、原則として報酬を支払うことは認められていません。前述のように、車上運動員や手話通訳者など特定の役割に限って、事前の届出を条件に報酬を支払うことが可能ですが、それ以外の選挙運動員は、自発的な意思による無償の協力が原則です。
もしボランティアに対して金銭を渡したり、過度な接待を行った場合、公職選挙法違反に問われる可能性があるため注意しなければなりません。余計なトラブルを避けるためにも、適切な関係性を築き、共に目標に向かって活動を進めることが大切です。
公示・告示後の選挙活動
選挙の公示日または告示日を迎えると、正式な選挙運動が解禁されます。この期間中、候補者は街頭演説や選挙カーの運行、ポスター掲示など、多岐にわたる活動を展開できます。
ただし、公職選挙法により、戸別訪問や飲食物の提供、署名運動などは禁止されているので注意してください。選挙運動期間については選挙の種類によって異なり、例えば衆議院議員総選挙では12日間と定められています。
選挙結果の承認・後処理
投票が終わると、すぐに開票作業が始まり、各地から結果が速報で伝えられます。ただし、これはあくまで暫定的なものであり、最終的な結果は後日、選挙管理委員会が正式に承認することで確定します。承認の過程では、すべての票が正しく集計されているか、公職選挙法のルールに則っているかなど、細かく確認が行われます。
そのうえで当選が確定すると、当選者には当選証書が交付され、正式に公職に就く資格が与えられます。また、全ての立候補者には、選挙運動にかかった費用を記した収支報告書の提出が義務付けられているので、期限内に忘れず提出しましょう。
2025年選挙基盤の構築と活用法
政策に説得力があっても、それを届けるための体制が整っていなければ選挙には勝てません。2025年の選挙では、従来の枠にとらわれず、組織、広報、資金、そしてデジタルといった複数の要素をどう連動させるかが問われます。
ここからは、選挙活動を支える体制・仕組みの整え方とその効果的な活用法について解説していきます。立候補を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
組織づくり
選挙戦を勝ち抜くためには、信頼できる人たちと「動ける体制」を整えることから始めましょう。例えば、後援会の設立は、支持者との連携を深め、選挙活動を円滑に進めるうえで欠かせません。
また、選挙事務所の設置も必要です。事務局長や会計責任者、広報担当など、それぞれの役割に適した人物を配置しておくと、選挙活動が格段に動かしやすくなります。地域ごとの支援者ともつながっておけば、票の広がり方にも勢いが出てくるはずです。
広報戦略
政策や想いを持っているだけでは、有権者の心には届きません。選挙では、それをどう伝えるかが結果を大きく左右します。演説やチラシの活用だけでなく、タイミングや言葉選び、視覚的な印象まで含めた設計が求められます。候補者の魅力や信念を、受け手が自然と共感できる形で表現することが大切です。
情報を発信するだけでなく、信頼を積み上げる行動として広報を捉える視点が不可欠といえるでしょう。
資金調達
選挙には想像以上に費用がかかります。事務所の維持費、印刷物、備品、交通費など、ひとつひとつは小さくても、全体ではかなりの負担となります。そのため、選挙戦を見据えた段階で、具体的な資金計画を立てておくことが欠かせません。
寄附の呼びかけや後援会費、クラウドファンディングなど、複数の手段を組み合わせながら、計画的に準備を進めることが大切です。必要なのは、潤沢な資金ではなく、支出を見越して動ける冷静な視点です。見込みと実際がずれないよう、資金面でも地に足のついた準備を整えておきましょう。
デジタル選挙戦略
今やネット抜きの選挙戦は考えにくい時代です。SNSやホームページ、メール配信など、デジタルをどう活用するかで、情報の広がり方もスピードも変わってきます。ただし、発信の内容や頻度、返信のスタンスなど、細かな戦略が求められるのも事実です。
リアルとデジタルをどう掛け合わせるか。そこに選挙戦の「勢い」が生まれます。得意な人を巻き込んで、早めに体制を整えておくのが得策でしょう。
まとめ
本記事では、2025年に予定されている各種選挙の日程から、立候補に必要な手続き、そして選挙戦を支える組織や広報・資金・デジタル戦略に至るまで、選挙活動全体の流れについて解説しました。
選挙に立候補することは、法的にも実務的にも多くの準備が必要となりますが、そのプロセスを一つひとつ丁寧に進めていくことで、効果的な選挙運動を展開できます。
しっかりと情報を整理し、準備を整えて、2025年の選挙に臨みましょう。