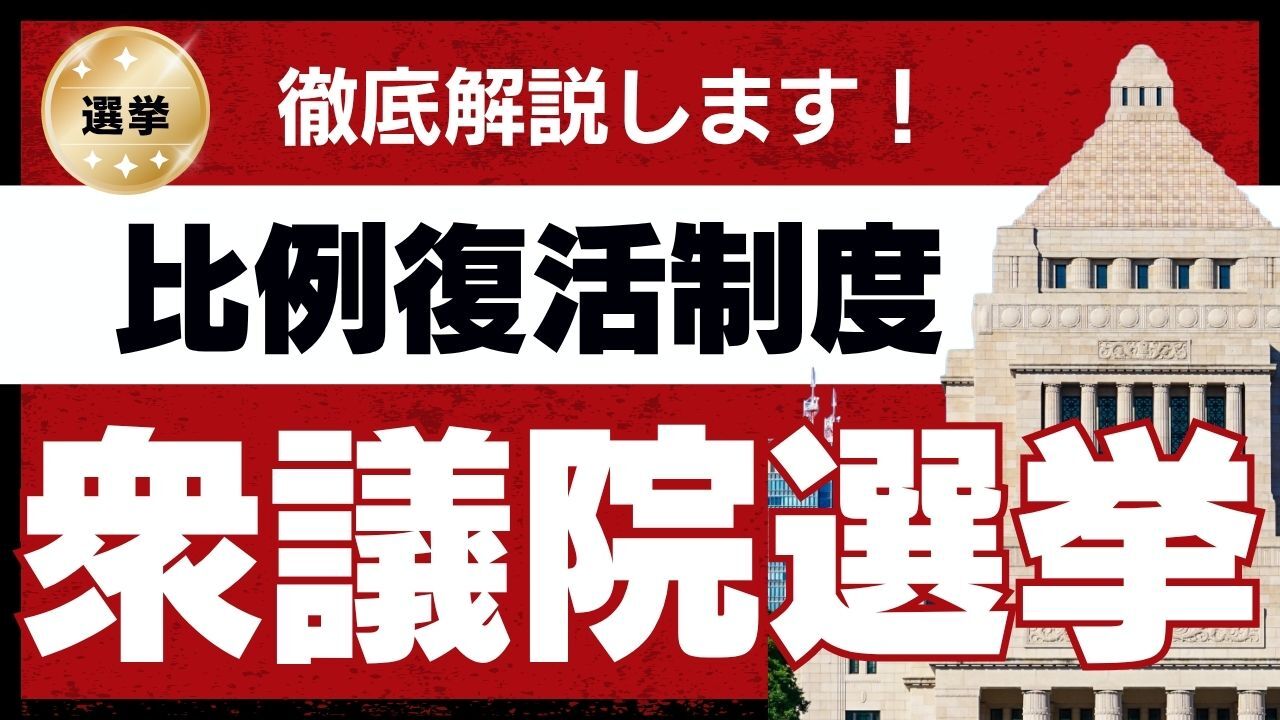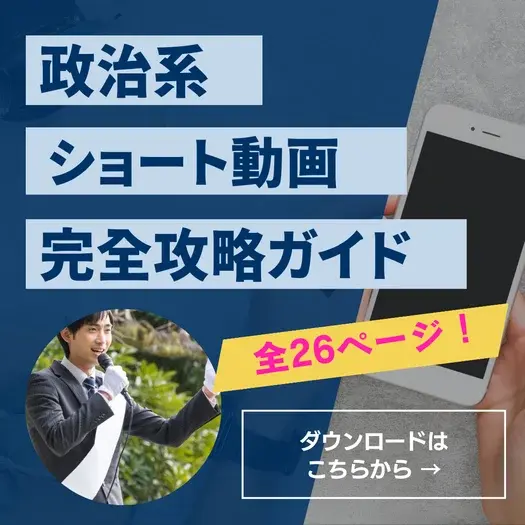はじめに
衆議院議員総選挙の開票速報を見ていると、必ずと言っていいほど耳にする言葉があります。
「候補、小選挙区では落選しましたが、比例代表で復活当選です」
選挙区で「負けた」はずの候補者が、なぜか「当選」している。この現象こそが、日本の衆議院選挙制度の最大の特徴である「比例復活」です。この制度については、「選挙区の民意を無視している」「ゾンビのように蘇る」といった批判的な意見も根強くあります。一方で、この制度には明確な「目的」があって導入されています。
なぜ、選挙区で敗れた候補者が国会議員になれるのでしょうか?
そこには、「小選挙区」と「比例代表」という2つの異なる選挙制度を組み合わせた、日本独自の複雑な仕組みが関係しています。この記事では、選挙ブログを運営する私たちだからこそお伝えしたい、衆議院選挙の根幹をなす「比例復活制度」について、その仕組み、ルール、メリット、そして問題点に至るまでを解説します。
目次
衆議院選挙の「2票制」の仕組み
比例復活を理解するためには、まず大前提として、現在の衆議院議員総選挙の仕組みを知る必要があります。1994年の政治改革により、それまでの中選挙区制に代わって導入されたのが「小選挙区比例代表並立制」です。この制度の最大の特徴は、私たち有権者が選挙で「2票」を投じる点にあります。
1票目:「小選挙区選挙」(候補者名を書く)
目的
地域の代表者(「人」)を選ぶ選挙
仕組み
全国を289の選挙区(小選挙区)に細かく分けて、有権者は立候補している「候補者の名前」を1人だけ書いて投票します。その選挙区で最も多くの票を獲得した1人だけが当選します。
メリット
選挙区が狭いため、候補者と有権者の距離が近く地域の課題が政治に届きやすくなります。また、1位の候補者だけが当選するため、政権交代が起こりやすい二大政党制に向いているとされます。
デメリット
1位以外の候補者に投じられた票は、すべて「死票」となり議席に反映されません。例えば、A候補が5万票、B候補が4万9千票だった場合、B候補に投じた4万9千票はすべて無駄になってしまいます。
2票目:「比例代表選挙」(政党名を書く)
目的
国民の多様な支持(「政党」)を議席に反映させる選挙
仕組み
全国を11の大きなブロック(例:東京ブロック、近畿ブロック、九州ブロックなど)に分けます。有権者は、「政党の名前」を書いて投票します。各政党が、そのブロック内で獲得した総得票数に応じて、議席が配分されます。(※ドント式という計算方法が使われます)
メリット
各政党の得票率に応じて議席が配分されるため、「死票」が少なく、少数政党の意見も国会に反映されやすくなります。
デメリット
議員個人の顔や政策が見えにくく、政党主体の選挙になりがちです。
比例復活とは何か?
衆議院選挙は、この「小選挙区」と「比例代表」という、性質の異なる2つの選挙を「並立」させて(=同時に行って)います。そして、多くの候補者はこの2つの選挙に同時に立候補(=重複立候補)します。
例:A党のBさん:
「東京1区」から小選挙区で立候補 + 「東京ブロック」から比例代表で立候補
ここで「比例復活」の定義が登場します。
比例復活(復活当選)とは?
小選挙区選挙で落選した候補者が、同時に立候補していた比例代表選挙の仕組みによって、議席を獲得すること。小選挙区という「個人戦」では負けたものの、所属政党が比例代表ブロックで獲得した「団体戦」の議席によって救済され、当選する。これが比例復活の正体です。この制度があるため、衆議院選挙は「小選挙区で勝つ」ことだけがゴールではありません。
たとえ小選挙区で負けても、
1.どれだけ「惜しい負け方」をしたか
2.自分の所属政党が、比例代表でどれだけ票を集めたか
が、当落を分ける第2の戦いとなるのです。
比例復活が起きるための厳格なルール
では、小選挙区で負ければ誰でも復活できるのでしょうか?
答えは「No」です。比例復活には非常に厳格なルールが定められており、ある候補者が比例復活するためには、以下の条件をすべてクリアしなければなりません。
条件1:重複立候補していること (重複立候補)
これが大前提です。
小選挙区選挙「だけ」に立候補している候補者は、小選挙区で負けた時点で「落選」が確定します。比例復活の権利はありません。比例復活の権利を得るには、出馬の時点で「小選挙区」と「比例代表」の両方にエントリー(重複立候補)している必要があります。
条件2:小選挙区で落選していること
当たり前のようですがこれも条件です。
もし重複立候補していた候補者が「小選挙区で勝利」した場合、その候補者は「小選挙区の当選者」となります。その場合、比例代表のリストからは自動的に除外され、比例代表の議席は、比例のリストの次の順位の候補者に回されます。
条件3:「供託金没収点」以上の得票を得ていること
ここからが重要です。
小選挙区選挙には「供託金」という制度があり、立候補者は法務局に300万円を預けます。これは、売名目的などの無責任な立候補を防ぐためです。この供託金は、選挙で一定以上の票を獲得すれば返還されますが、得票数が少なすぎると没収されます。
そのボーダーライン(没収点)は、「小選挙区の当選者の得票数の10分の1 (10%)」です。そして、この供託金を没収された候補者(=当選者の10分の1の票も取れなかった候補者)は、たとえ重複立候補していても、比例復活する権利を失います。
(例)
当選者Aさん:100,000票
落選者Bさん: 9,000票
→ Bさんは当選者の10% (1万票) に届かなかったため、供託金300万円は没収。
→ 同時に、比例復活の権利も失い、「完全落選」となります。
これは「泡沫候補」が比例復活することを防ぐための、非常に重要な足切りルールです。
条件4:所属政党がそのブロックで比例議席を獲得していること
個人が条件を満たしても、所属する「政党(団体戦)」が議席を獲得できなければ復活はできません。例えば、C党が「東京ブロック」で比例代表の票をほとんど獲得できず、議席の配分が「ゼロ」だった場合、C党に所属する重複立候補者は、たとえ惜敗率が高くても誰も復活できません。
条件5:「惜敗率」の順位で上位であること
これが、比例復活者を決める最後の、そして最も重要なルールです。多くの政党は、比例代表の名簿を作る際、重複立候補している候補者たちを「同順位」として扱います。(例:重複立候補者は全員「比例名簿 第3位」)
では、その「同順位」の候補者たちの間で誰を優先的に復活当選させるのか?
その優先順位を決める基準が「惜敗率」です。
惜敗率(せきはいりつ)とは?
その候補者が、小選挙区で「どれだけ当選者に肉薄したか」を示す割合。
計算式: 惜敗率 (%) = (落選した候補者の得票数) ÷ (当選した候補者の得票数) × 100
(具体例)
ある比例ブロックで、D党が比例復活の議席を「1枠」獲得したとします。
D党の重複立候補者(全員、小選挙区で落選)が2人いた場合:
候補者Xさん (東京1区)
当選者(他党): 100,000票
Xさんの得票: 90,000票
Xさんの惜敗率: (90,000 ÷ 100,000) = 90.0%
候補者Yさん (東京2区)
当選者(他党): 120,000票
Yさんの得票: 96,000票
Yさんの惜敗率: (96,000 ÷ 120,000) = 80.0%
この場合、惜敗率がより高い「Xさん(90.0%)」が、Yさんよりも優先され、D党の比例復活の1議席を獲得します。(※もちろん、XさんもYさんも、前述の「供託金没収点(当選者の10%)」はクリアしています)
得票数の「絶対数」ではYさん(9万6千票)がXさん(9万票)より多くても、あくまで「その選挙区の当選者に対して、どれだけ惜しかったか」という「割合」で決まるのがポイントです。
なぜ比例復活制度は存在するのか?
このように非常に複雑な比例復活制度ですが、なぜわざわざ導入されたのでしょうか。
それは、小選挙区制が持つ「大きな欠点」を補うためです。
メリット1:死票の救済(国民の多様な意見の反映)
最大の目的は「死票の救済」です。
前述の通り、小選挙区制は「1位以外はすべて切り捨て」という非常に過酷な制度です。
極端な話、全国のすべての小選挙区で、A党が51%、B党が49%の票を獲得し続けた場合、
小選挙区の議席: A党が100%、B党が0%
国民の支持率: A党 51%、B党 49%
となり、国民の意思と国会の議席構成が大きく乖離(かいり)してしまいます。
これでは、B党に投票した49%の国民の意思が政治に全く反映されません。そこで、比例代表選挙(と、そこでの復活制度)を組み合わせることで、「小選挙区では負けたが、政党としてはこれだけの支持を得ている」というB党の49%の支持を、比例議席として国会に反映させることができます。
これにより、小選挙区制の「民意の切り捨て」という欠点を補正し、より国民の支持率に近い議席配分を目指しているのです。
メリット2:惜敗者の救済(有能な政治家の確保)
政治家の中には、非常に有能で政策通であっても、選挙区の地盤(世襲や強力な後援会)を持たないために、選挙に弱い人がいます。また、全国的な人気はあっても、たまたま自分の選挙区に、自分より人気の高い強力なライバルがいる場合もあります。
もし小選挙区制しかなければ、そうした「有能だが選挙に弱い」候補者は、僅差で落選し続けることになり、国会から有為な人材が失われてしまいます。比例復活制度は、そうした「小選挙区では惜しくも敗れたが、国会で働く能力と実績のある政治家」を、党の比例議席で救済する「セーフティネット」としての役割も担っています。
メリット3:候補者擁立の促進(有権者の選択肢の確保)
もし比例復活がなければ、各政党は「絶対に勝てる選挙区」にしか候補者を立てなくなり、「どうせ勝てない選挙区(敵の地盤)」には候補者を立てない「不戦敗」を選ぶようになります。そうなると、有権者は投票したい政党の候補者がおらず、選択肢が極端に限られてしまいます。
比例復活という「敗者復活戦」の可能性があることで、政党は「小選挙区で勝つのは難しくても、惜敗率を稼いでくれれば復活のチャンスがある」と考え、不利な選挙区にも積極的に候補者を擁立するインセンティブが働きます。これにより、有権者の選択肢が広がるというメリットがあります。
比例復活制度の問題点と尽きない議論
一方で、この制度は導入以来、常に批判にさらされています。主な問題点は以下の通りです。
問題点1:「選挙区の民意」の否定(ゾンビ復活)
最も大きな批判がこれです。
小選挙区選挙は、有権者が「この人に地域を任せたい」という代表者を決める選挙です。そこで明確に「No」を突き付けられ、敗北した候補者が、別のルールで当選することに、有権者は強い違和感を覚えます。
・地元が選んでいない人物が、なぜ国会議員になれるのか
・民意によって倒されたはずの政治家が蘇る
このことから、比例復活は「ゾンビ復活」と揶揄されることが多く、制度の正当性に対する根本的な批判となっています。
問題点2:制度の複雑さによる不透明感
ここまで読んでお分かりの通り、この制度は非常に複雑です。
・重複立候補
・供託金没収点
・惜敗率
・ドント式
これらの仕組みを正確に理解している有権者は少数派でしょう。自分が投じた一票が、最終的にどのように作用して、誰が復活当選したのかが非常に分かりにくい。この「制度の不透明さ」が、有権者の政治不信や「選挙はよく分からない」という政治離れの一因になっているとも指摘されます。
問題点3:党執行部への権力集中
比例復活の前提となる「重複立候補」を認めるかどうか、また、比例名簿の順位(重複候補者を同順位にするか、特定の候補者を上位にするか)を決めるのは、「党の執行部(党本部)」です。これは、候補者の生殺与奪の権を党本部が握ることを意味します。
候補者は、選挙区の有権者の顔色をうかがうよりも、党執行部の意向に逆らわないように行動する(=イエスマンになる)インセンティブが働きます。「選挙区で落とされても、党に忠実であれば比例で復活させてもらえる」という構造が、政治家の緊張感を失わせ、派閥政治や党の独裁を強める要因になると批判されます。
問題点4:「惜敗率」の逆説
惜敗率が高い(=僅差で負けた)候補者を優先するというルールは、一見合理的です。しかし、これには逆説的な問題も含まれます。
A候補:楽な選挙区で選挙運動をあまりせず、惜敗率95%で負けた。
B候補:絶対に勝てないと言われる敵地(相手が超大物)で必死に戦い、惜敗率60%で負けた。
この場合、比例復活するのはA候補です。しかし、政治家としてのガッツや価値は、むしろB候補の方が高いのではないか?という議論です。惜敗率という「結果の数字」だけが評価基準となることで、本来救済すべき「困難な選挙区で奮闘した候補者」が切り捨てられ、単に「楽な選挙区で僅差で負けた候補者」が優遇されるという矛盾も指摘されています。
まとめ
今回は、衆議院選挙の「比例復活制度」について、その仕組みからメリット、デメリットまでを詳しく解説しました。比例復活とは、小選挙区で敗れた候補者が、比例代表の仕組みで当選する制度です。復活するには、「重複立候補」「供託金没収点(当選者の10%)以上の得票」「惜敗率の上位」など、厳格なルールをクリアする必要があります。
この制度のメリットは、「死票の救済」や「有能な人材の確保」であり、小選挙区制の欠点を補う役割があります。しかし、デメリットとして、「選挙区の民意の否定(ゾンビ復活)」や「制度の複雑さ」「党本部の権力強化」といった重大な問題点も抱えています。
比例復活制度は、「地域代表を1人だけ選ぶ」という分かりやすさ(小選挙区)と、「国民全体の支持率を議席に反映させる」という公平性(比例代表)という、二律背反する要求を両立させようとした結果生まれた、妥協の産物とも言えます。選挙速報で「復活当選」の報を聞いたとき、その裏側にある複雑なルールと、この制度が抱えるメリット・デメリットの両面を思い出すことで、日本の選挙と政治の「今」を、より深く理解できるのではないでしょうか。