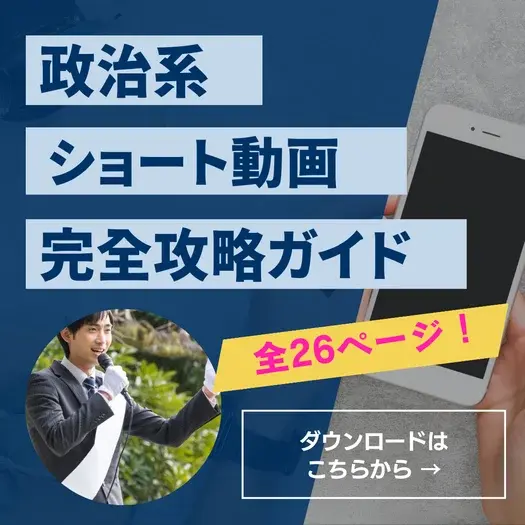はじめに
3年に一度の参議院選挙。
投票所で投票用紙を受け取った際、特に鳥取県、島根県、徳島県、高知県にお住まいの方は見慣れない選挙区の名前に戸惑った経験があるかもしれません。
「鳥取県及び島根県選挙区」
「徳島県及び高知県選挙区」
かつて、参議院選挙の「選挙区選挙」は、必ず「47都道府県」がそれぞれの単位(1票を投じるエリア)でした。「〇〇県選挙区」として、自分の住む都道府県の代表者を選ぶ。これが70年近く続いた、日本の選挙の「当たり前」でした。しかし、2016年の参議院選挙からこの「1県=1選挙区」という大原則が崩れました。
人口の少ない県同士がまるで市町村合併のように「合体」させられ、一つの選挙区として扱われることになったのです。これが「合区(ごうく)」です。
なぜ、長年の伝統を破ってまで、県と県を無理やりくっつけるような制度変更が行われたのでしょうか?この「合区」によって、私たちの選挙や政治はどのように変わったのでしょうか?この問題の根底には、日本国憲法が掲げる「法の下の平等」という理想と「各地域の代表者を国会に送りたい」という地方の切実な願いが衝突する、非常に深刻なジレンマが存在します。
この記事では、選挙ブログを運営する私たちだからこそお伝えしたい、参議院選挙の最も大きな争点の一つである「合区」について、その導入の背景にある「一票の格差」問題から合区が引き起こした新たな問題まで徹底的に解説します。
目次
「合区」とは何か? 2つの選挙区の誕生
まず、「合区」とは具体的にどのような制度なのかその定義から見ていきましょう。
合区の定義
「合区(ごうく)」とは、参議院の選挙区選挙において、人口が著しく少ない複数の都道府県を統合し、一つの選挙区とすることを指します。正式には「合同選挙区」と呼ばれ、参議院選挙は「選挙区選挙(地域代表を選ぶ)」と「比例代表選挙(全国の政党支持を選ぶ)」の2票制で成り立っています。
このうち「選挙区選挙」は、1947年(昭和22年)の第1回参議院選挙以来、一貫して「47都道府県」を単位として行われてきました。有権者は自分の住む「〇〇県」の候補者に投票し、各都道府県から(人口に応じて)決められた数の代表者を選出していたのです。
合区の対象となった「4県」
しかし、後述する「一票の格差」問題を是正するため、2015年に公職選挙法が改正され、この「1県1選挙区」の原則が崩れました。この改正により、全国で最も人口の少ない4つの県が、2つの「合区」の対象となりました。
1.鳥取県 + 島根県 → 「鳥取県及び島根県選挙区」
(定数:2人、3年ごとに1人を選ぶ「改選数1」)
2.徳島県 + 高知県 → 「徳島県及び高知県選挙区」
(定数:2人、3年ごとに1人を選ぶ「改選数1」)
この4県に住む有権者は、2016年の参議院選挙から、「鳥取県選挙区」や「徳島県選挙区」という単独の選挙区で投票することができなくなりました。彼らは、2つの県をまたいだ広大な選挙区で、隣の県の候補者も含めた中から、たった1人の代表者を選ばなければならなくなったのです。
なぜ合区は導入されたのか? 核心にある「一票の格差」問題
なぜ、これほど強引とも思える制度変更が断行されたのでしょうか。その唯一にして最大の理由が、日本の民主主義の根幹を揺るがす「一票の格差(いっぴょうのかくさ)」問題です。
「一票の格差」とは何か?
「一票の格差」とは、選挙区ごとの有権者数の違いによって、自分の一票が持つ「重み(価値)」に不平等が生じている状態を指します。簡単な例で考えてみましょう。
参議院選挙で、議員1人を選ぶのに、
A県(有権者100万人)では、100万人が1人の議員を選びます。
B県(有権者 50万人)では、 50万人が1人の議員を選びます。
この場合、B県の有権者の一票は、A県の有権者の一票に比べて議員を当選させる力が「2倍」あることになります。つまり、A県の有権者の「一票の重み」はB県の半分しかありません。これが「一票の格差」です。
憲法第14条:「法の下の平等」という大原則
この「格差」がなぜ大問題なのでしょうか。それは、日本国憲法第14条が「すべて国民は、法の下に平等であつて(中略)政治的(中略)関係において、差別されない」と定めているからです。この「法の下の平等」は、当然、選挙権にも適用されます。
「どこに住んでいるか」によって、自分の一票の価値が、他の人の5倍になったり、逆に5分の1になったりする状態は、この憲法の大原則に反するのではないか――。これが、長年にわたる憲法論争の核心でした。
最高裁判所の「違憲状態」判決
戦後、都市部への人口集中が進むにつれ、この「一票の格差」はどんどん拡大していきました。特に参議院は、「都道府県」という枠組みに固執したため、人口が最も多い東京都と最も少ない鳥取県との格差が過去には、報道や総務省公表値で「最大約4.7倍」と指摘された時期もあり格差の大きさが問題視されていました。全国各地で「格差は違憲だ」という訴訟が起こされ、その判断は最終的に最高裁判所に委ねられました。
最高裁は、長年にわたり「格差は望ましくない」としつつも、「都道府県を単位とすることには一定の合理性がある」として、選挙を無効にすることまではしませんでした。しかし、2010年代に入ると、ついに最高裁の堪忍袋の緒が切れます。最高裁はこの著しい格差を「違憲状態」であると厳しく断じました。
「違憲状態」とは、「法律(公職選挙法)の規定は憲法に違反している状態にあるが、すぐに選挙を無効にはしない。ただし、国会は合理的な期間内にこの異常事態を是正(法律改正)しなければならない」という、国会に対する「最後通牒」です。最高裁は「都道府県単位」という仕組み自体をゼロから見直すよう、国会に抜本的な改革を迫りました。
「このまま放置すれば、次の選挙は『違憲・無効』とする可能性もある」という、司法から立法(国会)への極めて重い警告でした。最高裁は「違憲状態」と判断した例があり、国会に対して早急な是正を求めてきました(選挙自体が無効とされたわけではありません)。
国会の「苦肉の策」としての「合区」
この最高裁の「最後通牒」を受け、国会(特に与党であった自民党)は、重い決断を迫られました。格差を是正する(=人口比に近づける)方法は、理論上2つしかありません。
1.都市部の定数を大幅に増やす
(例:東京、神奈川、大阪などの定数を増やす)
→ これを行うと、議員の総定数が際限なく増え続け、財政的にも非現実的です。
2.地方の定数を大幅に減らす
(例:人口の少ない県の定数を「1」から「0」にする)
→ これこそが「合区」です。
国会は、議員定数を(当面は)増やさないという方針のもと、苦肉の策として、「人口の少ない県同士をくっつけて、1つの選挙区として扱う」という後者の方法を選びました。これにより最も人口の少なかった鳥取県と島根県、徳島県と高知県が、それぞれ「定数1」の合同選挙区とされたのです。
この結果、参議院選挙の最大格差は、2013年選挙の「4.77倍」から、合区が導入された2016年参院選では最大格差が約3倍前後にまで縮小し、最高裁も「大きく拡大しているとはいえない」として、是正の進展を評価する判断を示しました。「合区」は、憲法が求める「一票の平等」という理想(司法の要求)と、地方の政治的実情との間で国会が絞り出したギリギリの妥協案だったのです。
合区が抱える根深い問題点
「一票の格差」は是正され、憲法上の要請には(一応)応えました。しかし、この「合区」という“劇薬”は、地方に深刻な「副作用」をもたらし、今なお強い反発と新たな問題を生み出し続けています。
問題点①:地域の代表が失われるという「地方の切り捨て」
これが、合区に対する最も根強く深刻な批判です。参議院は、衆議院とは異なり伝統的に「各地域の代表」が集う議院(「地域の府」)としての性格を強く帯びていました。47都道府県のそれぞれから、最低でも1人(改選ごと)の代表者が国会に送られ、その地域の声を中央政府に届ける。これが、地方の住民にとっての「当たり前」でした。
しかし、「合区」によってこの「当たり前」が失われました。
例えば、「鳥取・島根選挙区」(改選数1)では、
鳥取県出身のA候補(自民党)
島根県出身のB候補(立憲民主党)
が立候補した場合、どちらか1人しか当選できません。
もしA候補が当選すれば、島根県からは代表者が選出されなかったことになります。もしB候補が当選すれば、鳥取県から選出された議員はゼロになります。(※もちろん、両県出身の候補者が同じ政党から出ることもあり、その場合、党内の調整や知名度争いは熾烈を極めます)自分たちの県から、自分たちの地域課題(例:特定のインフラ整備、医療問題、産業振興)を直接国会に訴えてくれる代表者がいなくなる。これは、合区の対象となった県の住民にとって単なる感情論ではなく、「自分たちの声が国政に届かなくなる」「地方が切り捨てられた」という死活問題なのです。
問題点②:広大すぎる選挙区と有権者の混乱
選挙区が2県にまたがったことで、選挙運動や有権者の意識にも大きな影響が出ました。
候補者の負担増
候補者は、これまで「1つの県」で行っていた選挙運動を、「2つの県」という広大なエリアで行わなければならなくなりました。移動距離も時間もコストも単純に2倍以上となり、特に新人候補には極めて不利な戦いとなります。
有権者の混乱と関心の低下
鳥取県の有権者にとって、島根県の地域課題は分かりにくく、島根県出身の候補者には親近感が湧きません(逆もまた然り)。「結局、誰がどの地域の代表なのか分からない」「隣の県の候補者には投票したくない」といった意識が働き、結果として投票先を選びきれず投票率の低下につながるのではないかと懸念されています。
問題点③:政党の地方組織の弱体化
国政政党(特に自民党や立憲民主党)の地方組織は、基本的に「都道府県連(県連)」という単位で構成されています。「合区」は、この県連同士の関係性をも破壊しました。本来、隣県同士でライバル関係にあることもある2つの県連が、選挙では協力して「たった1人の候補者」を応援しなければならない。あるいは、候補者調整に失敗し、同じ政党の「鳥取系候補」と「島根系候補」が潰し合う「骨肉の争い」になる可能性すらあります。
これにより、党の地方組織が混乱し弱体化するという問題も指摘されています。
「特定枠」という“妥協案”との関係
この「合区」によって生じた地方の強い反発、特に「自分たちの県の代表者がいなくなる」という不満に対応するため、比例代表にはいわゆる「特定枠」と呼ばれる制度が新設されました。(政党が名簿の特定候補を優先的に当選させる仕組み)この「特定枠」導入の「建前(表向きの理由)」はまさに「合区の救済」でした。
その論理はこうです。
「合区(例:鳥取・島根)で、候補者を1人しか立てられない。その結果、選挙区から出馬できなくなった、もう一方の県(例:鳥取)の現職議員を、党が比例代表の『特定枠』に指定して確実に当選できるように救済してあげよう」
これにより、
島根県出身の候補者 → 「選挙区」で当選
鳥取県出身の候補者 → 「特定枠(比例)」で当選
という形で、実質的に両県から(選挙の形は違えど)代表者を国会に送り込むことができる、という政治的な“アメ”として使われました。しかし、ご存知の通りこの「特定枠」はすぐにその目的を逸脱し、合区とは全く関係のない候補者を(党の都合で)優先的に当選させるための「党利党略の道具」として利用されるようになり、新たな民主主義の問題を生み出しています。「合区」という問題の“つじつま合わせ”が、さらなる「特定枠」といういびつな仕組みを生んでしまったのです。
まとめ
今回は、参議院選挙における「合区」について、その背景と問題点を掘り下げました。
合区とは
参議院選挙区選挙で、人口の少ない「鳥取・島根」「徳島・高知」の2県ずつを統合し、一つの選挙区としたこと。
導入の理由
憲法第14条「法の下の平等」に違反する「一票の格差」について、最高裁判所から「違憲状態」と厳しく断じられ、国会が格差是正のために断行した「苦肉の策」である。
最大の問題点
格差は是正された一方で、合区の対象となった県では「自分たちの県の代表者が国会に送れない」という事態が発生。「地方の切り捨て」であるとして、今なお強い反発が続いている。
政治的帰結
この合区への不満の受け皿として、比例代表に「特定枠」が導入されたが、これはこれで新たな問題を抱えている。「合区」問題は、日本の民主主義が抱える根本的なジレンマを象徴しています。
「一人一票の価値の平等(人口比例)」を徹底するのか?
それとも、「各地域の代表(都道府県単位)」を保障するのか?
この二つは、現在の人口動態の中では両立が極めて困難です。「合区」は、前者の「平等」を優先し後者の「地域代表」を犠牲にした結果です。もし、後者を優先するのであればそれは「一票の格差」を容認することになり最高裁の判断、ひいては憲法14条の理念と衝突します。
このジレンマを根本的に解決するには、「参議院の役割とは何か」「都道府県を単位とすることに、憲法違反を乗り越えるほどの合理性があるのか」といった国家のあり方、あるいは憲法改正の議論にまで踏み込まざるを得ません。「合区」という一見地味な選挙ルールは、実はそれほどまでに重く、深い問いを、私たち国民に突きつけているのです。