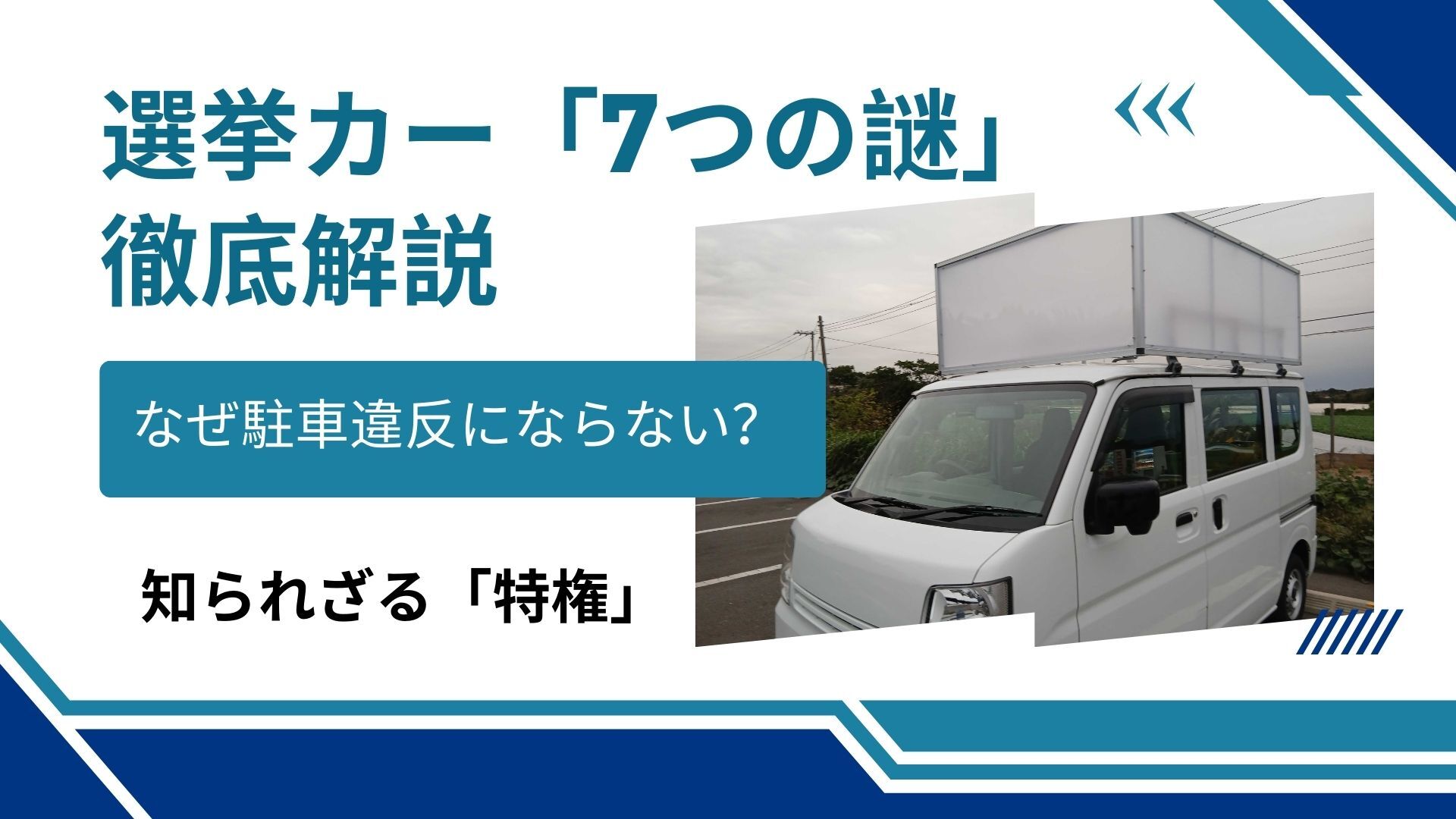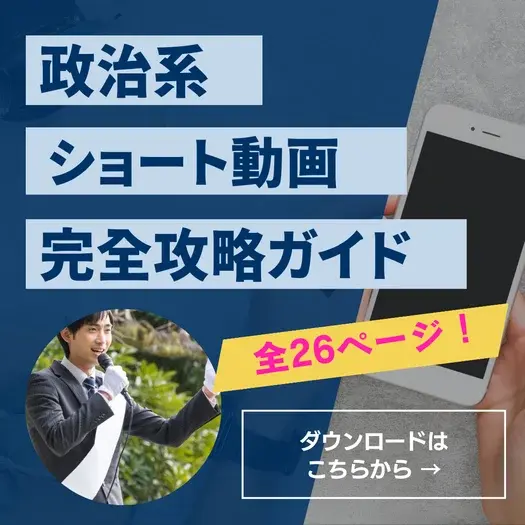はじめに
選挙の季節になると、街に活気(あるいは喧騒)をもたらす「選挙カー」。
その姿を見て、私たちは候補者の訴えに耳を傾ける一方で、こんな素朴な疑問を抱きませんか?
・あんな交差点のど真ん中に停めて駐車違反じゃないの?
・あのド派手な看板、車検に通るの?サイズ違反じゃない?
・大音量で走るのに警察の許可は要らないの?
「うるさい」と感じるだけでなく、まるで「治外法権」かのような特権を持っているようにさえ見えます。
しかし、それらの運用には、すべて「理由」があります。
この記事では、選挙カーにまつわる「知られざるルール」と「からくり」について、公職選挙法と道路交通法という2つの法律を軸に、徹底的に解き明かしていきます。
目次
1:選挙カーには「2種類」ある(すべての基本)
まず、この問題を理解するための大前提として、私たちが「選挙カー」と呼んでいる車には、法律上、まったく異なる2種類が存在することを知る必要があります。
1.「選挙運動用自動車」(=本番の車)
* いつ走る?:
選挙の「告示日(公示日)」から「投票日の前日」までの選挙期間中だけ。
* 何ができる?:
候補者の名前を連呼したり、「投票してください」とお願いしたりする「選挙運動」ができます。
* 特徴:
選管が交付する「標旗(ひょうき)」と呼ばれる旗やステッカーを付けています。公職選挙法(公選法)で厳しく規制されます。
2.「政治活動用自動車」(=普段の車)
* いつ走る?:
選選挙期間「以外」の、普段の政治活動。
* 何ができる?:
「〇〇党のXXです。政策を訴えます」といった「政治活動」はできますが、「私に投票してください」という「選挙運動」は絶対にできません。
* 特徴:
政党や候補者の名前を載せた看板(「立て看板」の扱い)を車につけて走ります。
この2つは、適用されるルールも、警察への届け出の考え方も、まったく違います。この区別が、すべての謎を解くカギとなります。
2:あの「ド派手な看板」のサイズ、違法じゃないの?
まずは、車の「見た目」のルールです。特に選挙期間「外」に走っている政治活動用の車(2番の車)は、候補者の顔写真が車体全体を覆っているものもあり、「あれは違法な改造車じゃないの?」と感じるかもしれません。これには「公職選挙法」と「道路交通法(道交法)」の、2つの法律が関係します。
1. 政治活動用(普段)の車の看板ルール
政治活動で使える看板(「立札」や「看板」の類)は、公選法で厳しくサイズや枚数が決まっています。政党用、個人用でルールが異なりますが、候補者個人の看板は「〇枚まで」と定められています。
その「看板」を、車に取り付けて走っているのが「政治活動用自動車」ですが、ここでのポイントは、「看板の積載」という扱いです。道交法では、車検証に記載された「幅」「長さ」「高さ」を超えるものを積む場合、出発地の警察署長に「制限外積載許可」を申請しなければなりません。
つまり、車体からはみ出すような巨大な看板(特に高さ)をつけている車は、本来、この「制限外積載許可」を警察から受けていなければ、道交法違反となります。(※ただし、後述する「本番」の車とのルールの違いから、政治活動用の車は車体サイズに収まるように作られるのが一般的です)
2. 選挙運動用(本番)の車の看板ルール
一方、選挙期間中(本番)の車は、公選法第141条で「看板」や「ポスター」のルールが厳密に定められています。そして、道交法の観点では、公選法で認められた選挙運動用の看板・ポスターについては、「車体の寸法(車検証のサイズ)を超えないもの」と解釈・運用されています。
結論として、選挙期間中の選挙カーは、車検証に記載された長さ・幅・高さの「範囲内」で看板などを設置しなければなりません。
もし、この範囲内で設置されているのであれば、それは道交法上の「積載」とはみなされず、別途、警察の「制限外積載許可」は不要となります。多くの選挙カーが、車体ピッタリの「箱」を載せているのは、このルールを守っているからです。
3:「政治活動」で走るのに、警察の許可は要らないの?
「謎2」と関連しますが、「選挙期間外」に、政党や候補者の名前を大音量で流しながら走る「政治活動用自動車」。あれは警察に届け出ているのでしょうか?結論から言うと、「車を走らせる」こと自体には、警察の許可は原則不要です。
公道(道路)は、許可がなければ走ってはいけない場所ではありませんので問題は「走り方」です。
1. 「道路使用許可」が必要なケース
皆さんが「許可が必要では?」と思うのは、主に「スピーカー(拡声器)の使用」と「演説」でしょう。道路交通法 第77条では、「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」をする場合、警察署長の「道路使用許可」が必要と定めています。
具体的には、
* デモ行進や、お祭りのお神輿
* 道路上で、演説会や集会を開き、人や車を止めてしまう行為
* 路上でチラシ配りや募金活動を行う行為
などが該当します。
単に「政治活動カーが走っている」だけでは、これに該当しません。しかし、もし駅前ロータリーなどで車を停め、その場に人を集めて「街頭演説会」を開き、一般の交通を妨げる場合は、当然「道路使用許可」が必要になります。
2. 「騒音」に関する届け出
むしろ、警察との関係で重要なのは「騒音」です。拡声器(スピーカー)の使用については、道交法ではなく、各都道府県が定める「騒音防止条例(または公害防止条例)」で厳しく規制されています。「何デシベル以下」「学校や病院の周りでは使用禁止」「夜間(例:午後8時〜午前8時)は使用禁止」といったルールです。
政治活動であっても、この条例は守らねばなりません。実務上は、トラブルを避けるため、地元の警察署(交通課や警備課)に「こういうルートで、こういう活動をします」と事前に「相談」や「届け出(情報提供)」をしているケースがほとんどです。
これは法律上の「許可」とは違いますが、警察側も「誰が何をやっているか」を把握でき、住民から「うるさい!」と通報があった場合も「〇〇党が活動中です」と対応できるため、お互いにとって必要な手続きとなっているのです。
4:なぜ選挙期間中は「朝8時〜夜8時」だけなのか?
「選挙期間中」の選挙カーは、謎3の「騒音防止条例」とは別のルールで縛られています。これは公職選挙法 第140条の2で定められており、選挙運動(連呼行為)のために拡声器を使えるのは「午前8時から午後8時まで」と、法律で全国一律に決まっています。
これは、有権者の「静穏(せいおん)に暮らす権利」を守るためです。(※ただし、街頭演説(車を停めて行う演説)の最中は、例外的に夜8時を過ぎても拡声器が使えることになっています。これもまた、よく「うるさい」と問題になる点です)
5:選挙期間中は「駐車違反」にならない、最大のカラクリ
さて、ここが本題です。
選挙期間中、選挙カーは平気で「駐車禁止」の場所や、ひどい時には「交差点の近く」に停まって演説をしています。なぜ警察は取り締まらないのでしょうか。これは「特権」のように見えますが、実は「法律の解釈」と「運用の優先順位」の「からくり」が隠されています。
建前:「駐車」ではなく「停車」である
まず、警察が使う「理屈」では、道交法で「駐車」と「停車」は明確に区別されています。
* 駐車:
運転者が車から離れて「すぐに運転できない」状態。または、5分を超える荷物の積み下ろしや、客待ち・荷待ち。
* 停車:
人の乗り降りや、5分以内の荷下ろし。または、運転者が車内にいて「すぐに運転できる」状態。
選挙カーは、候補者やウグイス嬢が演説している間も、運転手は必ず運転席に座っています。これは「すぐに移動できる状態」、すなわち「停車」であると解釈されます。「駐車禁止」の標識がある場所の多くは、「停車」は禁止されていません(「駐停車禁止」の場所は別です)。「彼らは駐車違反をしているのではなく、合法的な『停車』をしているだけだ」というのが、警察の第一の建前です。
6:なぜ「交差点(駐停車禁止)」でも許されるのか?
「なるほど、『停車』か。でも、交差点の中や、その端から5メートル以内は『駐停車禁止』のはずだ。そこで演説しているのは、どう説明するんだ」
その通りです。道交法 第44条では、交差点、横断歩道、バス停(※)などは「駐停車禁止」と定められており、本来は1秒たりとも停まってはいけません。
ここからが、本当の「からくり」であり、一般に「特権」と呼ばれる部分です。
結論から言えば、「公職選挙法に基づく正当な選挙運動(街頭演説)は、道路交通法の一部の規定(駐停車禁止)よりも優先される」という、最高裁判所の判例(判決の先例)が存在するからです。
1. 「選挙の自由」 vs 「交通の安全」
日本国憲法は「民主主義」を国の基本としており、その根幹をなす「選挙」が公正に行われることを非常に重視しています。公職選挙法は、その「選挙の自由」を保障するための法律です。一方、道路交通法は、「交通の安全と円滑」を守るための法律です。
もし、選挙カーが「街頭演説(公選法で認められた正当な行為)」のために、駐停車禁止場所(道交法の規制対象)に「一時的に停車」した場合、どちらの法律を優先すべきか?
2. 最高裁の「お墨付き」
過去の裁判でこの点が争われました。
最高裁判所は、「公職選挙法に基づく選挙運動のための街頭演説は、公共の利益(民主主義)のための正当な業務行為であり、そのために必要な範囲での一時的な停車は、社会通念上やむを得ないものとして道路交通法の駐停車禁止の規定は適用されない(=違反にならない)」という趣旨の判断を下しています。
つまり、「選挙」という、国にとって非常に重要な活動のためであれば、交通ルールの一部(駐停車禁止)は、一時的に「免除」されるという「お墨付き」を司法が与えているのです。
7:では、選挙カーは「何でもあり」なのか?
「じゃあ、選挙カーは無敵の特権じゃないか」と思うかもしれませんが、もちろん「無制限」ではありません。
1. 警察は「取り締まらない」が「監視」はしている
警察官は、この「最高裁のお墨付き」を知っているため、選挙カーが駐停車禁止場所に停まっていても、即座に「違反だ」と取り締まることは(原則として)しません。しかし、彼らは「交通の安全」を守る義務もあります。そのため、選挙カーの演説場所が、「著しく」交通の妨害になっている場合(例:救急車が通れない、交差点を完全に塞いで大渋滞を引き起こしているなど)、警察官は演説を中断させ、車を移動させるよう「指示・命令」することができます。
この警察官の「交通整理」の指示に従わなければ、今度は公務執行妨害や道交法の別の違反に問われる可能性があります。
2. 「停車」でなくなった瞬間アウト
そして、最大の注意点はあくまで「停車」であることです。もし、街頭演説の最中に運転手まで車から降りてマイクを握ったりビラ配りを手伝ったりして「すぐに運転できない」状態になったら?
その瞬間、それは「停車」ではなく「駐車」になります。「駐車」は、最高裁が認めた「選挙運動に不可欠な一時的行為」の範囲を超えますので、そうなれば、警察は「駐車違反」として即座に取り締まることが可能です。
まとめ:ルールを知れば、選挙の見方が変わる
選挙カーにまつわる「謎」をまとめましょう。
1.選挙カーには「本番用」と「普段用」があり、ルールが違う。
2.看板サイズは、「本番用」は車検証の範囲内が原則。
3.「政治活動」での走行自体に許可は要らないが、「演説場所」や「騒音」は道交法や条例で規制される。
4.選挙期間中の「駐車違反スルー」は、「停車」であるという建前と、「選挙運動(公選法)は道交法に優先する」という最高裁の判例(特権)に基づいている。
5.ただし、「著しい交通妨害」や「運転手が車を離れた(駐車)」場合は、即座にアウト。
これらのルールは、一見すると「選挙の特別扱い」であり不公平に感じるかもしれません。しかしそれは、「交通の安全」という利益と、「民主主義の根(選挙の自由)」という利益を天秤にかけた結果、法律と司法が導き出した、非常に高度な「妥協点」でもあるのです。
次に選挙カーを見かけたら、その停め方や、運転手の動きにもぜひ注目してみてください。彼らがいかに法律の「ギリギリのライン」を攻めているかが、見えてくるかもしれません。