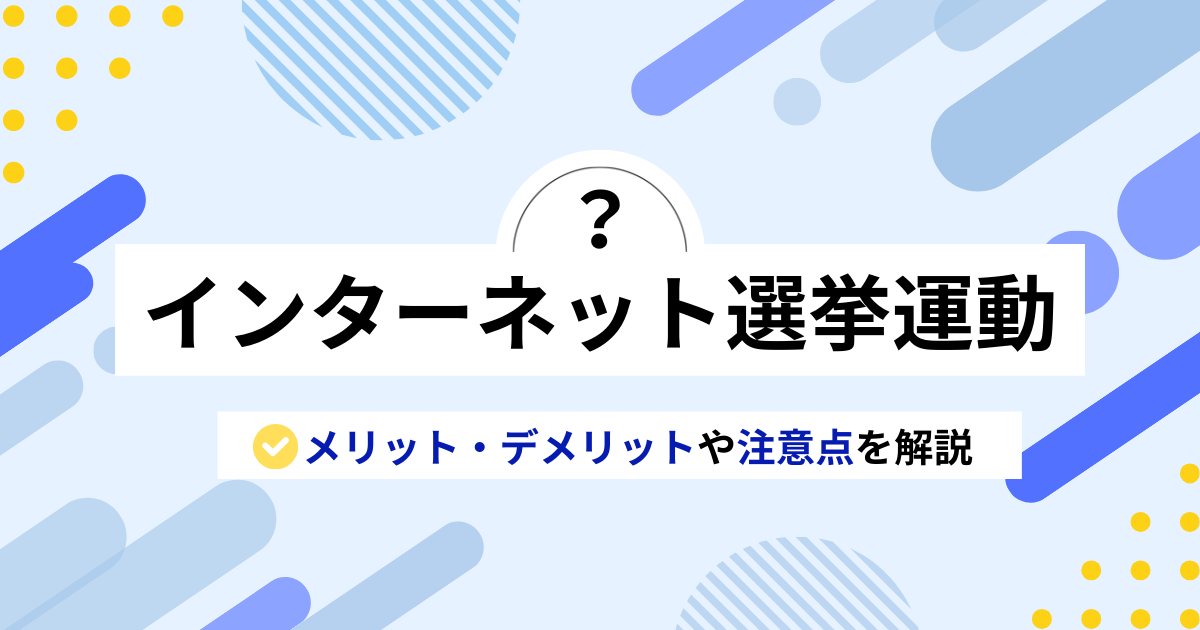はじめに
SNSや動画配信などを活用したインターネット選挙運動は、いまや選挙戦略に欠かせないものとなっています。しかし、発信の自由度が高い反面、公職選挙法に基づくルールや制限も多く、誤った運用は思わぬ違反につながるおそれがあります。
本記事では、インターネット選挙運動の基本から、できること・できないこと、活用するメリット・デメリットをわかりやすく解説します。これから本格的にネットを活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
インターネット選挙運動の基本情報
インターネット選挙運動は、選挙期間中にウェブサイトやSNSなどを活用して、有権者に向けて投票を呼びかける行為を指します。ここではまず、その制度がいつ、どのような背景で解禁されたのかを整理しておきましょう。
インターネット選挙運動はいつから解禁された?
日本でインターネット選挙運動が正式に解禁されたのは、2013年の参議院議員通常選挙からです。同年4月に公職選挙法が改正され、選挙運動期間中に限って、候補者や政党、一般有権者によるウェブサイトやSNSを通じた選挙運動が可能となりました。
これにより、従来のビラや街頭演説だけでなく、インターネット上でも広く政策やメッセージを届けることができるようになりました。ただし、電子メールの利用制限や、投票日当日の投稿制限など、守るべきルールも多く存在します。
インターネット選挙運動が解禁された背景とは?
インターネット選挙運動が解禁された背景には、有権者の情報収集手段の多様化と、投票率の低下があります。
特に若年層を中心に、テレビや新聞よりもネットから政治情報を得る傾向が強まり、従来の選挙手法だけでは訴求力が届きにくいという課題が顕在化していたのです。また、海外ではインターネットを活用した選挙戦略が成果を上げている事例も多く、日本国内でもその活用を求める声が高まっていました。
こうした流れを受けて、各党による協議や法整備が進み、2013年にインターネット選挙運動が一部解禁されるに至りました。
インターネット選挙運動で「できること」と「できないこと」
インターネット選挙運動が解禁されたとはいえ、何でも自由にできるわけではありません。法律で明確に認められている行為と、禁止されている行為が存在します。ここでは、インターネット選挙運動で「できること」と「できないこと」を解説します。
インターネット選挙運動でできること
選挙期間中であれば、公職選挙法の範囲内でインターネットを利用した選挙運動が認められています。代表的な「できること」は以下の通りです。
- 選挙期間中に、候補者本人や政党がSNS(X、Facebook、Instagramなど)を使って投票を呼びかける
- 街頭演説の予定をホームページやブログ、SNSで告知する
- YouTubeなどの動画サイトで、演説・討論会・街頭活動などを配信する
- 有権者に向けて、候補者・政党から選挙運動用の電子メールを送信する(※条件あり)
- SNSやウェブサイト上に選挙運動用ポスターやビラの画像を掲載する
特にSNSや動画配信は、有権者との距離を縮める有効な手段になります。継続的な発信を意識して、日々の活動や想いをタイムリーに届けていきましょう。
インターネット選挙運動でできないこと
続いて、インターネット選挙運動において「やってはいけないこと」を確認しておきましょう。以下の行為は、公職選挙法で禁止されています。
- 選挙運動期間外に選挙運動を行う
- 投票日当日にSNSやブログで投票を呼びかける
- 候補者以外の一般有権者が、電子メールで選挙運動を行う
- 匿名・偽名での発信や、連絡先を明記しない投稿
- 満18歳未満の者が選挙運動に関与する
上記はいずれも罰則の対象となり得る行為です。うっかり違反を防ぐためにも、関係者全員でルールを共有し、投稿前には内容とタイミングをしっかり確認する習慣をつけましょう。
インターネット選挙運動のメリット
インターネットを活用することで、従来の選挙運動では難しかった情報発信や有権者との接点が広がります。ここでは、インターネット選挙運動のメリットを3つ解説します。
時間や場所にとらわれず情報発信ができる
インターネット選挙運動が解禁される以前、候補者が有権者に情報を届ける手段といえば街頭演説や戸別訪問、電話による案内、ポスター掲示、ビラ配布など、時間や場所に制約のある方法に限られていました。移動や人手を要するうえ、物理的な距離の壁もあり、広範囲に情報を届けるには限界がありました。
一方、ネットを活用すれば、24時間いつでも情報を発信でき、地理的な制約もありません。たとえば、早朝や夜間でもスマートフォンから有権者に向けて政策を発信できますし、街頭演説の様子をそのまま動画で投稿すれば、現場に来られなかった有権者にもメッセージを届けることができます。
また、新聞やテレビなどのマスメディアでは取り上げられにくい情報も、インターネットならダイレクトに発信できます。
このように、限られた資源のなかでより多くの有権者との接点を築けるようになったことは大きなメリットといえるでしょう。
若い世代の投票を促すことができる
若い世代の政治参加を促すきっかけになることも、インターネット選挙運動のメリットです。
長年、若年層の投票率の低さは大きな課題とされてきました。政治に関心があっても、情報に触れる機会が少なかったり、候補者との接点がなかったりすることが、行動につながらない要因となっていたのです。
しかし、SNSや動画配信など、若い世代にとって身近なメディアを使った選挙運動が可能になったことで、候補者の人柄や考えを直接届けやすくなりました。たとえば、XやInstagramに政策のポイントを簡潔にまとめたり、ショート動画で日々の活動を紹介したりすることで、自然と関心を引きやすくなります。
こうした日常的な発信は、若者が政治をより身近に感じるきっかけとなり、「自分も投票してみようかな」と思う意識の変化を促すことにつながります。
選挙運動にかかる費用を抑えることができる
選挙運動にインターネットを活用することで、コストを抑えつつ効率的に情報を届けることが可能になります。
従来の選挙運動では、ポスターやビラの印刷費、会場の設営費、人件費など、多くのコストが発生していました。特に広い地域に情報を届けようとするほど、コストはかさむ一方でした。
その点、SNSやウェブサイトでの発信は、投稿自体に費用がかからず、気軽に情報を届けることができます。また、街頭演説の様子を動画サイトにアップすれば、何度も視聴してもらえるため、現地での演説にかける時間や交通費の削減にもつながります。
限られたリソースで効率よく多くの有権者へアプローチできる点は、インターネット選挙運動ならではのメリットです。
【無料配布】誰でも容易に使える「ショート動画攻略マニュアル」※資料ダウンロード
インターネット選挙運動のデメリット
多くのメリットがあるインターネット選挙運動ですが、気をつけなければならない点もいくつかあります。ここからは、インターネット選挙運動における3つのデメリットを解説します。
誹謗中傷やデマが拡散されるおそれがある
インターネットを活用した選挙運動では、情報発信の手軽さゆえに、誤情報や根拠のない批判が拡散されてしまうリスクも伴います。
SNSの特性上、ひとつの投稿が瞬く間に広範囲へ拡散されてしまうため、内容次第では候補者や陣営の評価に深刻な影響を及ぼしかねません。特に、事実関係を歪曲した投稿や、悪意のある切り抜き動画などが拡散されてしまうと、事後対応に追われるばかりか、信頼回復に相当な労力を要することが想定されます。
このようなリスクを回避するためには、日常的に公式チャネルから正確で信頼性の高い情報発信を行い、有権者との信頼関係を築いておくことが重要です。また、万が一の炎上や誤情報の流布に備え、広報対応や法務面を含めた初動フローを事前に整備しておくことも、有効なリスクマネジメントといえるでしょう。
なりすまし被害が発生するおそれがある
インターネット選挙運動では、候補者本人や政党の名前をかたった「なりすましアカウント」の出現にも注意が必要です。
見た目が本物そっくりの偽アカウントから不適切な投稿がなされた場合、それを信じた有権者の誤解を招き、候補者の信頼に影響を与えるおそれがあります。実際に、実在する候補者の名前や顔写真を使って偽アカウントが作られ、誤解を招く投稿が拡散された例も報告されています。
こうした被害を防ぐには、公式アカウントの認証を取得しておく、プロフィールや投稿で「本人」であることを明確に示す、怪しいアカウントや投稿を発見した際には速やかに通報・報告するなど、日常的な対策が求められます。
不正アクセスや情報流出のおそれがある
インターネットを利用する以上、情報セキュリティ面のリスクは常に意識しておかなければなりません。とりわけ懸念されるのが、外部からの不正アクセスやマルウェアによる情報窃取です。
たとえば、ウイルスやトロイの木馬といった悪質なプログラムを通じて、支援者名簿や連絡先などの個人情報が盗まれ、外部に流出するケースがあります。こうした事態が発生すれば、候補者や陣営への信頼は大きく損なわれ、選挙活動そのものへの影響も避けられません。
そのほかにも、過剰なアクセスによりサーバーを一時的にダウンさせる「DDoS攻撃」や、感染端末を遠隔操作する「ボットネット」を悪用したサイバー攻撃なども報告されています。
万全を期すには、セキュリティ設定の見直しやサーバー監視体制の構築を、選挙準備段階から意識しておくことが重要です。
インターネット選挙運動の注意点とは
インターネットを活用した選挙運動は法律上のルールを正しく理解していないと、思わぬ違反につながるおそれもあります。ここでは、特に注意したい5つのポイントを解説します。
投票日にSNSで投票を呼びかけるのはNG
選挙運動が認められているのは、公職選挙法により「選挙の公示日(または告示日)から投票日の前日まで」と定められています。つまり、投票日当日はインターネットも含めて、すべての選挙運動が禁止です(公職選挙法第129条)。
そのため、投票日当日にSNSで「○○候補に投票をお願いします」「○○党を応援しましょう」といった投稿を行うことは違反行為となります。加えて、選挙期間中に投稿した内容を投票日に再投稿(リポスト・シェア)する行為も、事実上の選挙運動と見なされる可能性があるため注意してください。
もし投票当日に発信する場合は、「投票に行こう」といった一般的な呼びかけにとどめ、特定の候補者名や政党名に言及しないようにしましょう。
投稿や動画配信をする際は連絡先を明記すること
インターネットを利用した選挙運動では、ウェブサイトやブログ、動画配信サービスなどを通じて情報を発信する際、発信者の連絡先を明記することが法律で義務付けられています(改正公職選挙法第142条の3第3項)。これは、有権者が発信内容に疑問や確認事項があった場合に、発信者と連絡を取れるようにするための措置です。
ここでいう「連絡先」とは、電子メールアドレス、返信用フォームのURL、X(旧Twitter)のユーザー名など、インターネットを介して発信者に連絡するために必要な情報を指します。ただし、XやFacebookなどのSNSに関しては、投稿者のユーザー名が表示され、プロフィールページから直接連絡を取ることが可能な仕組みとなっているため、あらためて投稿内に連絡先を記載する必要はありません。
他の立候補者の誹謗中傷はNG
インターネット選挙運動において、他の候補者や政党に対する誹謗中傷や虚偽の情報を拡散する行為は、厳しく禁止されています。公職選挙法第235条第2項では、特定の候補者の当選を妨げる目的で虚偽の事項を公にしたり、事実を歪めて公表したりする行為が処罰の対象となると明記されています。
たとえば、他の候補者の過去の発言を意図的に切り取って誤解を招くように投稿したり、根拠のない噂話をSNSで拡散したりすることは、選挙の公正性を損なう重大な違反行為です。このような行為は、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪にも該当する可能性があり、刑事罰が科されることもあるため注意しなければなりません。
健全な選挙運動を行うためにも、他の候補者に対する誹謗中傷は絶対に避けましょう。
18歳未満の選挙運動はNGだが、外国人は可能
インターネット選挙運動では、発信者の属性にも注意しなければなりません。まず、満18歳未満の者が選挙運動を行うことは、公職選挙法で禁止されています(公職選挙法第137条の2)。これにはSNSでの投稿やシェア、動画配信など、ネット上の活動も含まれます。
加えて、18歳未満の人を選挙運動に関わらせることも違法となるので、スタッフを起用する際は年齢の確認が必要です。ただし、文書の発送や接待、運搬といった“選挙運動にあたらない作業”については関与が認められています。
一方、外国人については選挙権こそ有していませんが、選挙運動を行うこと自体は禁止されていません。したがって、外国人が特定の候補者を支持する内容をSNSで発信することや、選挙運動に参加することは可能です。しかし、金銭や物品を提供する「寄附行為」などには制限があるため、注意が必要です。
年齢や国籍によるルールをきちんと把握したうえで、健全な選挙運動に取り組みましょう。
SNS運用の対価として報酬を渡すことはNG
公職選挙法では、選挙運動に従事する者への報酬の支払いを原則として禁じており、これに違反した場合は「買収罪」に問われる可能性があります(公職選挙法第221条)。
特に注意したいのが、SNSでの投稿や動画配信など、インターネットを通じた活動への報酬です。こうした発信に対して報酬を支払うことは、法律に違反する行為とされ、処罰の対象になります。
ただし例外もあり、たとえば車上運動員(いわゆるウグイス嬢)や手話通訳者、要約筆記者など、特定の職種に限っては、選挙管理委員会への事前届出を条件に、法定の範囲内で報酬を支払うことが認められています。しかし、SNSの運用や動画配信といったインターネット上の活動は、これらの例外には該当しません。
候補者や陣営の関係者は、報酬の取り扱いについて誤解がないよう、選挙管理委員会に事前に確認するなどして、慎重に対応することが求められます。
インターネット選挙運動のよくある質問
インターネット選挙運動に関するルールや運用方法については、迷いやすいポイントも多くあります。ここからは、候補者や陣営スタッフからよく聞かれる疑問をピックアップし、回答とともにご紹介します。
支援者が電子メールを使って選挙運動するのはOK?
支援者(一般有権者)が電子メールを使って選挙運動を行うことは、公職選挙法で禁止されています。公職選挙法では、選挙運動における電子メールの使用について、候補者本人や政党など特定の者に限り認められています(公職選挙法第142条の3第1項)。
また、候補者が支援者に対して、電子メールの転送を促すことも、違反と見なされるため注意が必要です。支援者が選挙運動を行う場合は、SNSやブログなど、法律で認められた方法を利用するようにしましょう。
選挙期間外に政策や活動をSNSで発信するのはOK?
選挙期間外に政策や活動内容をSNSで発信することは可能です。ただし、その内容が「選挙運動」と見なされる場合、公職選挙法に抵触する恐れがあります。
選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として行われる活動を指します。したがって、選挙期間外に「○○選挙で私に投票してください」といった投稿を行うことは、事前運動と見なされ、違法となります。
一方で、日常的な政治活動として、政策や活動報告をSNSで発信することは問題ありません。選挙運動と政治活動の境界は曖昧な場合もあるため、投稿前に内容を慎重に確認し、必要に応じて選挙管理委員会などに相談することをおすすめします。
投票日に他人の投稿をシェアやリポストするのはOK?
投票日当日は候補者本人はもちろん、陣営スタッフや支援者も含め、いかなる選挙運動も行うことができません(公職選挙法第129条)。そのため、過去に投稿された応援メッセージや投票呼びかけの投稿などを、投票日当日にリポストやシェアする行為もNGとなります。
たとえ自分が作成した投稿でなくても、それを拡散することで「当選を目的とした新たな選挙運動」とみなされる可能性があるので注意してください。
まとめ:正しい知識でインターネット選挙運動を味方につけよう
本記事では、インターネット選挙運動が解禁された背景から、具体的にできること・できないこと、活用するメリット・デメリットなどを詳しく解説してきました。
SNSや動画配信などを活用することで、効率よく有権者との接点をつくることが可能になりますが、ルールを正しく理解しないまま運用すると、思わぬ違反につながるおそれもあります。公職選挙法をしっかり把握したうえで、自身の選挙戦にインターネットを戦略的に取り入れていきましょう。