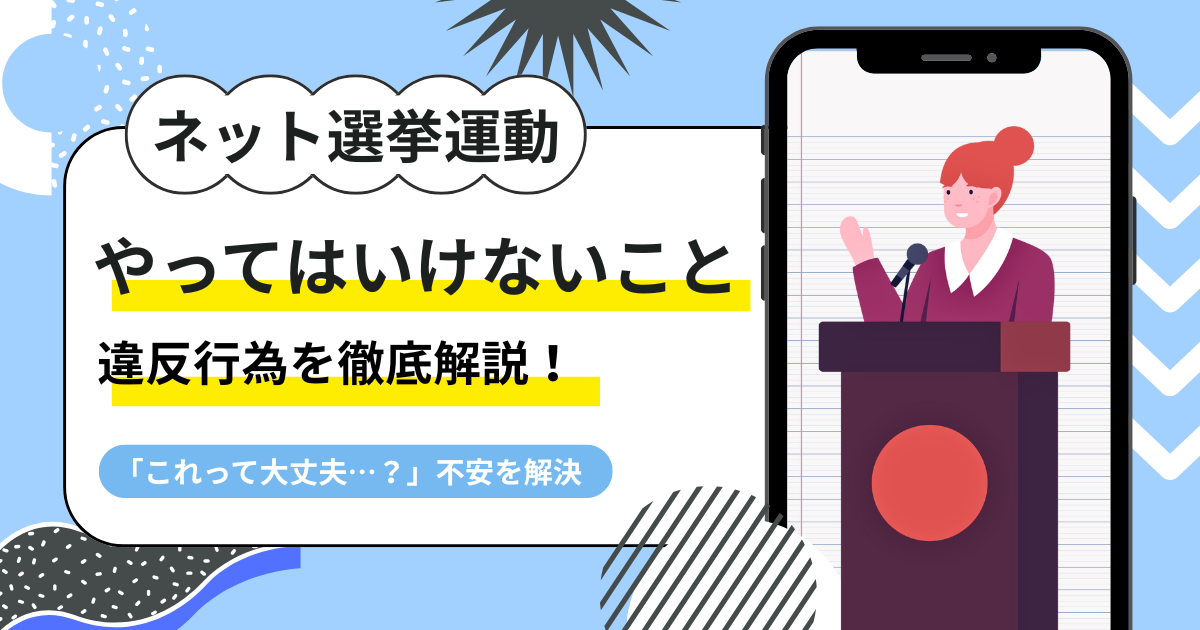はじめに
SNSやウェブサイトを活用した選挙運動が可能になった今、インターネット上での情報発信は候補者にとって欠かせない活動のひとつとなっています。
しかし、公職選挙法には細かなルールがあるため、「この投稿は大丈夫?」「スタッフがうっかり違反しないか心配…」と感じる方も多いのではないでしょうか。たとえ悪意がなかったとしても、法律に違反すれば処罰を免れることはできません。
本記事では、公職選挙法に照らし合わせながら、ネット選挙運動でやってはいけない行為や注意点をわかりやすく解説します。
目次
ネット選挙運動とは何か
インターネットを使った選挙運動が認められるようになったことで、選挙のあり方は大きく変化しました。ここではまず、ネット選挙運動が導入された時期・背景や、その重要性を解説します。
ネット選挙運動の導入時期とその背景
日本でインターネットを活用した選挙運動が正式に認められたのは、2013年の公職選挙法改正によるものです。それ以前は、選挙運動におけるインターネットの利用は「文書図画の頒布」と見なされ、原則として禁止されていました。
この改正の背景には、インターネットの普及と有権者の情報収集手段の多様化があります。特に若年層を中心に、政治や選挙に関する情報をインターネットから得る人が増加しており、従来の選挙運動手法では対応しきれない状況となっていました。
また、海外でのインターネット選挙運動の成功事例も影響を与えました。例えば、2008年のアメリカ大統領選挙では、バラク・オバマ候補がSNSを駆使して支持を広げたことが注目され、日本でも同様の手法を取り入れるべきだという声が高まりました。
このような社会的要請を受けて、2013年の法改正により、ウェブサイトやブログ、SNSを利用した選挙運動が可能となりました。ただし、電子メールの利用には制限が設けられるなど、一定のルールが定められています。
ネット選挙運動の重要性
現代の選挙戦において、インターネットの活用は欠かせない要素となっています。特にSNSやウェブサイトは、有権者との接点を広げるうえで実践しやすく、多くの候補者が積極的に活用しています。
最近では、テレビや新聞ではなく、ネットで情報を集める有権者が増えており、特に若い世代にはその傾向が顕著です。実際、2022年の参議院選挙では、インターネットで得た情報が投票先を選ぶ際の“決め手”になったという声も多く見られました。公益財団法人・明るい選挙推進協会の調査によると、ネット選挙運動に触れた人のうち61.8%が「投票先を決める際に役に立った」と回答。これは選挙公報や政見放送を上回る数字で、ネット上の情報発信が有権者の判断に大きく影響していることがわかります。
また、ネット選挙運動は、時間や場所に制約されずに情報を発信できるため、従来の選挙運動手法では届きにくかった層へのアプローチも可能となります。
参照:公明党
ネット選挙運動でできること
公職選挙法の改正により、インターネットを活用した選挙運動が一定の条件下で認められるようになりました。ここでは、具体的に何ができるのかを整理していきます。
ウェブサイトの利用
公職選挙法の改正により、候補者や政党はホームページ、ブログ、SNS(XやFacebookなど)を通じて選挙運動を行えるようになりました。これにより、政策の紹介、日々の活動報告、投票の呼びかけなど、インターネットを活用した情報提供の幅が大きく広がっています。
具体的には、以下のようなオンライン媒体での選挙運動が認められています。
- ホームページやブログ、SNSでの投稿や掲載
- SNSやLINEなどのメッセージ機能を通じた発信
- YouTubeなどの動画配信サービスでの動画投稿やライブ配信
なお、選挙運動用のウェブサイトには、電子メールアドレスや返信用フォームのURLなど、連絡先の明記が義務付けられています。また、選挙運動期間外の更新や、投票日当日の新規投稿には制限があるため、運用には十分な注意が必要です。
電子メールの利用
選挙運動期間中、候補者や政党は電子メールを活用して有権者に情報を発信することが認められています。
ただし、無制限に送信できるわけではなく、公職選挙法に基づいた厳格なルールが設けられています。それらを満たさない場合は公職選挙法違反となるおそれがあります。
主な条件は以下の通りです。
- 送信先の制限:選挙運動用電子メールの送信の求め・同意をした者、もしくは政治活動用電子メールを継続的に受信している者への送信に限られる(無差別送信は禁止)
- 記録保存義務:選挙運動用電子メールの送信の求め・同意があったこと、もしくは政治活動用電子メールを継続的に受信していることなどの事実を証する記録を一定期間保存しなければならない
- 表示義務:送信者の氏名、選挙運動用メールである旨の記載、受信拒否の意思表示に関する案内および受信拒否通知を行う際に必要となるメールアドレスなどの連絡先の明記
公職選挙法違反になるネット選挙運動とは
ネット選挙運動が可能になったとはいえ、すべてが自由に認められているわけではありません。ここからは、公職選挙法上で禁止されている行為について、代表的な違反例を解説します。
選挙運動を選挙運動期間外に行う
インターネットを活用して早めに情報発信を始めたいと考える候補者や陣営スタッフも多いかもしれません。ですが、選挙運動が認められているのは、公示日または告示日から投票日の前日までと法律で定められています(公職選挙法第129条)。
つまり、その期間外に「○○候補に投票をお願いします」といった発信を行うと、「事前運動」と見なされ、公職選挙法違反になるおそれがあります。SNSの投稿はもちろん、動画配信や電子メールの送信も対象です。
つい早めに告知したくなる場面もあると思いますが、開始時期を誤るだけで法令違反になるリスクがあるため、選挙運動開始のタイミングには十分注意しましょう。
ネット上の有料広告を政党以外が利用する
選挙期間中、ネット広告を活用して候補者の認知を広げたいと考える陣営も多いはずです。しかし、公職選挙法では、有料のインターネット広告を使った選挙運動は「政党等(候補者届出政党、衆・参名簿届出政党、確認団体など)」に限られており、個人の候補者が出稿することはできません(公職選挙法第142条の6)。
たとえば、候補者本人やその後援会が自費でSNS広告や検索連動型広告を出すことは法律違反となります。これは、資金力の差が選挙の公平性を損なうことを防ぐための措置です。
有権者への情報発信は大切ですが、広告の扱いには十分な注意が必要です。
政党・候補者以外が電子メールで選挙運動を行う
選挙期間中、電子メールを使って選挙運動を行えるのは、候補者本人や政党に限られています。これは公職選挙法で明確に定められており、それ以外の人物がメールで投票を呼びかける行為は原則として禁止されています(改正公職選挙法第142条の4第1項)。
たとえば、陣営スタッフが候補者の代理として選挙運動用メールを送信したり、有権者に対して「このメールを転送してください」と促したりする行為も、違反となるおそれがあります。
SNSでの発信と違って、電子メールは密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことなどの理由から規制が厳しくなっています。電子メールを活用する際は、「誰が送信するのか」「どこまでが許されるのか」を正しく理解し、スタッフにも周知しておくことが大切です。
選挙運動用の電子メールやHPを印刷して配る
選挙運動用のウェブサイトや電子メールの内容をプリントアウトして頒布することは、公職選挙法で禁止されています(公職選挙法第142条、第243条)。このような行為は「法定外文書図画の頒布」とみなされ、違反とされる可能性があります。
公職選挙法第142条では、選挙運動のために使用できる文書図画の種類が限定されています。これには、選挙運動用の通常葉書、ビラ、パンフレット、選挙公報などが含まれますが、インターネット上の情報を印刷して配布することは含まれていません。
選挙運動においては、インターネット上での情報発信と紙媒体での配布には明確な区別があり、それぞれに適用されるルールが異なるため注意が必要です。
投票日当日にネット上で呼びかける
選挙運動が認められているのは、原則として投票日の前日までです。投票日当日は、たとえインターネット上であっても選挙運動は行えません(公職選挙法第129条)。これは公職選挙法第129条に基づく規定で、SNSや動画配信サイトなども対象です。
たとえば、「今日は投票日です!○○候補に清き一票を!」や「最後まで応援よろしくお願いします」といった投稿を、投票日当日に行うと公職選挙法に抵触する可能性があります。また、過去の投稿をリポスト・いいねする行為も同様に注意が必要です。
満18歳未満の者が選挙運動を行う
選挙権が18歳に引き下げられたことで、若年層の政治参加が進んでいますが、選挙運動を行えるのは「満18歳以上」の者に限られています。たとえ選挙に関心があったとしても、満18歳未満の者が選挙運動を行うことは公職選挙法で禁止されています(公職選挙法第137条の2)。
SNSで「○○候補を応援しています」と投稿する行為も、選挙運動に該当すると判断されれば違反となる可能性があります。候補者や陣営スタッフは、ボランティアとして協力を申し出る未成年者がいた場合、その活動が法に抵触しないか十分に確認し、適切な範囲で関わってもらうよう配慮する必要があります。
氏名や身分を偽ってネット上で投稿や配信をする
ネット上では匿名での発信が一般的ですが、選挙運動に関しては話が別です。公職選挙法では、氏名や身分を偽って選挙運動を行うことを禁じています(公職選挙法第235条の5)。
たとえば、実在しない人物になりすましてSNSで投稿を行ったり、所属していない団体名を名乗って情報発信をした場合、違反とみなされる可能性があります。また、スタッフやボランティアが故意に偽名を使って発信した場合でも、候補者が責任を問われるリスクがあります。
インターネットは拡散力が高いため、投稿者の身元や発言内容の管理は陣営として徹底しておくべきポイントです。
連絡先を記載せずにネット上で投稿や配信をする
インターネットを利用した選挙運動では、発信者の連絡先情報を明示することが法律で定められています。具体的には、ウェブサイトやブログなどで選挙運動用の文書や画像を掲載する際、電子メールアドレスや返信用フォームのURL、SNSのユーザー名など、発信者に直接連絡が取れる情報を表示しなければなりません(改正公職選挙法第142条の3第3項)。
この表示義務は、有権者が発信者に直接連絡を取れるようにするための措置です。連絡先を記載せずに投稿や配信を行った場合、公職選挙法に違反する可能性があるため注意が必要です。
なお、掲示板などに書き込む際も、各投稿ごとに連絡先情報を明示する必要があります。ハンドルネームのみの記載では不十分であり、連絡先が確認できるリンク先を設けるなどの対応が求められます 。
ただし、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSでは、投稿時にユーザー名が自動的に表示され、プロフィールページから直接連絡を取ることが可能なため、追加で連絡先を記載する必要はありません。
落選目的で虚偽情報を流す
選挙戦において、対立候補の信用を貶める目的で虚偽の情報をインターネット上に流す行為は、公職選挙法で厳しく禁じられています。特に、SNSやブログ、動画配信などを通じて、事実無根の情報を発信することは、選挙の公正性を著しく損なう重大な違反行為とされます(公職選挙法第235条第2項)。
このような行為は、候補者本人だけでなく、陣営スタッフや支持者が行った場合でも、候補者の責任が問われる可能性があります。万が一、連座制が適用されれば、当選が無効となるリスクも否定できません。
そのため、陣営内での情報発信に際しては、内容の真偽を十分に確認し、慎重な対応が求められます。
候補者のウェブサイトを改ざんする
選挙戦において、候補者のウェブサイトは政策やメッセージを伝える重要な情報源です。その内容を不正に改ざんしたり、偽のページを作成して発信したりする行為は、選挙の公正性を著しく損なう重大な違反です。
公職選挙法第225条第2号では、候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は処罰されると定められています。さらに、無断で他人のウェブサイトにアクセスし、内容を変更する行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条および第11条に基づき、不正アクセス罪でも処罰される可能性があります。候補者や陣営スタッフは、ウェブサイトのセキュリティを強化し、改ざんのリスクを最小限に抑えるための対策を講じるとともに、万が一不正アクセスの兆候を発見した場合は、速やかに関係機関に報告し、適切な対応を行うことが重要です。
選挙違反がもたらす重大な影響
ネット選挙運動におけるルール違反は、知らなかったでは済まされません。ここでは、ネット選挙違反がもたらすリスクについて確認しておきましょう。
選挙違反によって失うリスクを理解する
選挙違反が発覚した場合、候補者や陣営が受ける影響は極めて大きく、法的な処罰にとどまらない深刻なダメージが生じます。以下は、想定される主なリスクです。
- 禁錮や罰金などの刑事罰が科される
- 選挙権・被選挙権の停止措置を受けるおそれがある
- 「違反候補」という印象を持たれ、当選が難しくなる
そもそも選挙違反は、刑法や公職選挙法などに基づき「犯罪」として扱われる行為です。そのため、違反が確認されれば処罰の対象となるだけでなく、選挙への立候補すら制限される場合もあります。
また、ネット選挙では情報の拡散が早いため、違反行為が瞬時に広まりやすいのが実情です。一度失った信用は簡単には戻りません。だからこそ、選挙運動に関わる全員が、法的なルールを理解したうえで行動することが重要です。
連座制が適用される場合を把握する
選挙違反の責任は、違反行為をした本人だけにとどまりません。公職選挙法に定められている「連座制」では、候補者自身が違反に直接関与していなくても、選挙運動に関わる人物に一定の刑罰が確定した場合、候補者の当選が無効になることがあります。
対象となるのは、たとえば運動責任者や秘書、親族、選挙運動を計画・統括する立場にある人物などです。これらの関係者が買収などの違反で禁錮以上の刑、あるいは罰金刑を受けた場合、候補者にも法的な影響が及ぶ可能性があります。
特に、出納責任者や総括主宰者など、陣営の中枢にいる人物の有罪が確定した場合には、裁判を経ずに自動的に当選が無効となることも。そうなれば、候補者側は自身で裁判を起こし、失職を回避するために争わなければなりません。
こうしたリスクを避けるには、候補者本人はもちろん、陣営全体がルールを正しく理解し、細心の注意を払って選挙運動を進めることが不可欠です。
ネット選挙運動に関するよくある質問
ネット選挙運動に取り組むなかで、「これは大丈夫?」「このケースは違反になる?」と迷うこともあるはずです。ここでは、候補者やスタッフからよく聞かれる疑問をQ&A形式で分かりやすくまとめました。
ネット選挙運動は公示日前に行っても問題ないですか?
選挙運動が認められるのは、原則として公示日(または告示日)から投票日前日までの期間に限られています。これはネット上での発信にも適用され、公示日前に「○○候補に投票を」といった投稿を行うと、公職選挙法違反となるおそれがあります。
選挙運動のつもりがなくても、候補者の当選を意図していると見なされる発信は「事前運動」と判断される可能性があります。候補者やスタッフは、選挙期間外の発信内容に細心の注意を払いましょう。
なお、政策の紹介や日常活動の報告など、「政治活動」の範囲内であれば問題ありませんが、表現の仕方ひとつで選挙運動と取られることもあるため、運用時には法的な基準を事前に確認しておくことをおすすめします。
Xやフェイスブックで選挙運動を行っても問題ないですか?
選挙期間中であれば、候補者や政党はXやFacebookといったSNSを活用して、選挙運動を行うことが認められています。ただし、公職選挙法に定められたルールに従う必要があり、自由に投稿できるわけではありません。
たとえば、発信内容には候補者の連絡先を明示する義務があり、匿名アカウントでの投稿やなりすまし行為は禁止されています。また、投票日当日の投稿も選挙運動と見なされる可能性があるため避けなければなりません。
候補者本人でなくてもネット選挙運動をしても大丈夫ですか?
公職選挙法の改正により、候補者本人だけでなく、有権者も一定の条件のもとでインターネットを活用した選挙運動に参加できるようになりました。たとえば、Xやフェイスブックで「○○候補を応援します」と投稿すること自体は、選挙期間中であれば認められています。
ただし、誰もが自由に何でもできるわけではありません。たとえば、未成年者(満18歳未満)の選挙運動は認められていませんし、電子メールを使った投票の呼びかけは、候補者・政党以外は禁止されています。
陣営スタッフやボランティアが発信を担う場合も、投稿内容や使用する媒体が法律に反していないかを事前に確認しておくことが大切です。
選挙運動中に、相手候補からSNSで名誉を傷つける投稿をされた場合はどうすればいいですか?
選挙期間中、SNS上での情報発信が活発になるなか、誹謗中傷や虚偽の情報によって名誉を傷つけられるケースも見受けられます。たとえ相手が候補者であっても、公職選挙法や刑法に違反する内容であれば、法的な対処が可能です。
まず行うべきは、該当の投稿を記録として保存しておくことです。スクリーンショットの取得や、投稿日時・アカウント情報などの証拠確保が重要です。そのうえで、選挙管理委員会や警察に相談し、必要に応じて名誉毀損や侮辱罪での対応を検討することができます。
また、公職選挙法第235条では、虚偽の事実を公表する行為に対して処罰規定が設けられており、一定の条件を満たせば刑事責任を問える場合もあります。選挙に影響を及ぼす可能性があるため、冷静に対処しつつ、早めに専門家や関係機関に相談しましょう。
まとめ:ネット選挙運動はルールを守って効果的に活用しよう
本記事では、ネット選挙運動でやってはいけない行為や選挙違反がもたらす影響、よくある疑問について解説してきました。
SNSやウェブサイトを活用した選挙運動は、有権者と直接つながる有力な手段となり得ますが、一方で、公職選挙法に違反すれば当選の無効や信頼の失墜といった重大なリスクを招きかねません。
候補者本人はもちろん、陣営スタッフや支援者も含め、関係者全員が正しい知識を持ち、法令に沿った運用を行うことが重要です。ルールを踏まえたうえで、戦略的かつ誠実な情報発信を心がけましょう。
関連記事
初めての選挙戦、名簿はどうやって集め、作るのか?
現場で見た!選挙でうまくいく人の共通点を解説
選挙にかかるお金の考え方|コストと効果の話
選挙で成果が出る人・出ない人の違いとは?
どぶ板選挙×空中戦|ハイブリッド戦略とは?
選挙時の空中戦とは?オンライン時代の選挙で重要性が高まる理由
どぶ板選挙って何?オンライン時代でもどぶ板選挙が重要な理由
「握手×SNS」が勝敗を分ける!現代選挙の勝ちパターン。地上戦とネットのハイブリッド戦略とは?
ネット選挙運動の落とし穴。「やってはいけないこと」を知らずに違反していませんか?
公職選挙法違反になりやすいSNS投稿の違反例と対策を紹介
【無料配布】誰でも容易に使える「ショート動画攻略マニュアル」※資料ダウンロード
{% module_block module...