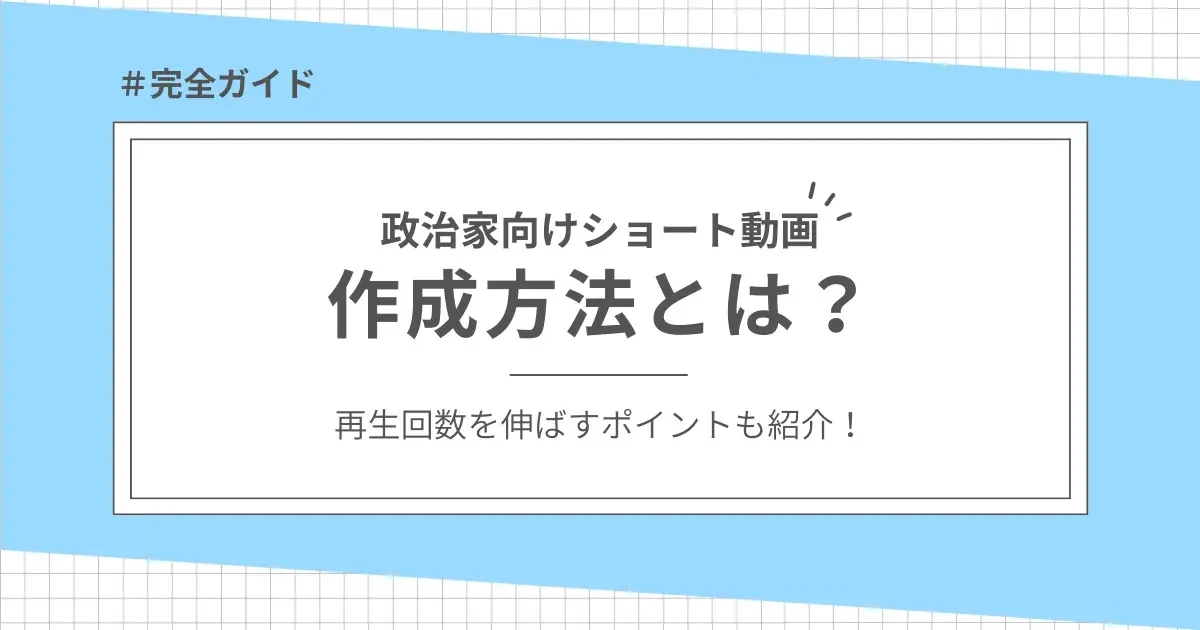SNSの政治活動禁止事項とは?投稿時に注意すべきポイントを解説
【無料配布】誰でも容易に使える「ショート動画攻略マニュアル」※資料ダウンロード
{% module_block module...【無料配布】誰でも容易に使える「ショート動画攻略マニュアル」※資料ダウンロード
現代において、有権者に考えや活動を伝える手段はますます多様化しています。そのなかでも近年注目を集めているのが「ショート動画」です。
数十秒という短い尺で人柄や理念を伝えることができ、日常的にSNSを利用する若い世代にも自然に届きやすい点が特徴です。「自分も取り入れるべきだろうか」と悩んでいる政治家の方も多いと思いますが、基本を押さえれば決して難しいものではありません。
本ブログでは、ショート動画の基礎から、政治家が活用すべき理由やメリット、具体的な作り方、再生回数を伸ばすためのポイントまでを、わかりやすく解説していきます。
ショート動画を活用するにあたっては、まずその基本を理解しておくことが大切です。「そもそもショート動画とは何なのか」「どんなプラットフォームで発信できるのか」を知っておくことで、自分の活動に合った取り入れ方を見つけやすくなります。以下で詳しく見ていきましょう。
ショート動画とは、その名の通り短い時間で完結する動画を指します。長くても1分程度、多くは15〜30秒ほどの尺に収められるのが一般的です。短い時間で要点を伝えられるため、移動中やちょっとした休憩時間など、視聴者の隙間時間に自然と再生されやすいのが特徴です。なかでもスマートフォンとの相性が良く、多くの場合は縦型で表示されます。
YouTubeが「YouTubeショート」というサービス名を打ち出していることから、「ショート動画=YouTubeショート」と認識されることもありますが、実際にはTikTokやInstagramでも同じ形式の動画が普及しています。政治家にとっては、限られた時間で自分の思いや政策を簡潔に伝えられる新しい発信手段といえるでしょう。
これまで議会中継といえば、ケーブルテレビや自治体の専用ウェブサイトを通じて配信されており、視聴者はごく一部に限られていました。しかし、発信チャネルの見直しによって、視聴者数が大幅に伸びた自治体も存在します。
たとえば新潟県新発田市では、CATVを通じて行っていた議会中継をYouTube配信へと切り替えた結果、視聴者数が約10倍に増加したと報告されています。これは、視聴に特別な機器や契約を必要とせず、スマートフォンやPCで手軽にアクセスできる環境が整ったことが大きな要因といえるでしょう。
このように、配信方法の工夫ひとつで、有権者との接点を飛躍的に拡大できる可能性があるのです。
YouTubeショートは、世界的に利用者が多いYouTube内で展開されているショート動画機能です。国内でも幅広い世代に使われており、既存のYouTubeユーザーにそのままリーチできる点が大きな強みといえます。
特に、YouTubeは視聴履歴や関心に基づいて「関連動画」が表示される仕組みがあるため、政策や社会課題などテーマを絞った内容を発信すれば、関心の高い層に届きやすいのが特徴です。また、ショート動画を入り口として通常の長尺動画に誘導することで、より詳しい活動報告や政策解説を見てもらう流れをつくることも可能です。
TikTokは、ショート動画ブームの火付け役となったプラットフォームです。長尺動画は扱わず、短い動画に特化しているのが特徴で、特に10代〜20代といった若い世代に絶大な支持を得ています。
最大の魅力は、ユーザーの興味・関心に合わせて動画を届けるアルゴリズムの仕組みです。質の高い動画やトレンドに乗った動画は、一気に数万、数十万回と再生が伸びることも珍しくありません。また、編集機能も充実しており、音楽やエフェクトを簡単に組み合わせられるため、特別な機材がなくてもハイクオリティな動画を簡単に作成できます。
なお、アカウントを開設したばかりでも、投稿が必ず一定数のユーザーに配信される仕組みがあるので、初心者でも挑戦しやすいのもポイントです。
Instagramリールは、写真投稿SNSとして知られるInstagramに搭載されたショート動画機能です。Instagramはビジュアル重視のプラットフォームであり、おしゃれな写真やデザイン性の高い投稿が好まれる傾向にあります。リールでも、政治家の活動風景や政策のビジュアル化など、視覚に訴えかけるコンテンツが効果的です。
フォロワーとのコミュニケーションも活発に行われやすく、ストーリーズやライブ配信といった他の機能と組み合わせて利用することで、多角的な広報戦略を展開できます。若い世代の女性を中心に支持が厚いため、そうした層にアプローチしたい場合に特に有効です。
ショート動画はここ数年で一気に広まり、政治の分野においても活用の幅が広がりつつあります。では、具体的にどのような点で政治活動と相性が良いのか、詳しく解説していきます。
政治家というと、どうしても堅苦しいイメージを持たれがちです。政策や公約を理路整然と語っても、それだけではなかなか有権者の心に届きません。多くの人が本当に知りたいのは、制作だけでなく「この人はどんな人なのか」という人柄です。
その点、ショート動画を活用すれば、人柄や日々の取り組みを短い映像で自然に伝えることができ、親近感を持ってもらいやすくなります。たとえば地域での活動風景や地元の人との交流、時にはユーモアを交えた一面を見せることで、「思っていたよりも親しみやすそうな人だ」と感じてもらえることもあるでしょう。
こうした小さな積み重ねが、最終的に「この人なら信頼して応援したい」という気持ちにつながっていくのです。
政治家がショート動画を活用すべきもう一つの理由は、若年層へのリーチのしやすさです。今の若い世代は、テレビや新聞よりもSNSから情報を得ることが当たり前になっています。そのため、ショート動画を使えば、従来のメディアでは届きにくかった層にも自然に情報を届けることができます。
実際、SNS上では街頭演説や議会での発言を切り抜いたショート動画が数多く拡散されており、タイムパフォーマンスを重視する若者に好まれています。2022年の参院選では、参政党が数多くの切り抜き動画をきっかけに若年層から支持を集めた例もありました。
このように、短くキャッチーな動画は共感を呼びやすく、新しい支持層の獲得につながる可能性が高いのです。
「編集」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実際にはいくつかの作業を順番にこなしていくだけで、見やすく伝わりやすい動画に仕上げることができます。ここでは、YouTube動画編集の大まかな流れを以下7つのステップに分けてご紹介します。
ショート動画を活用するメリットとしてまず挙げられるのが、ターゲット層や潜在層に届きやすいという点です。各プラットフォームには独自のアルゴリズムがあり、視聴者の興味や視聴履歴に合わせて動画が自動的におすすめ表示されます。そのため、特定の政策に関心を持つ層はもちろん、これまで政治に関心が薄かった潜在層にまでリーチできる可能性があります。
たとえば、子育て支援について発信すれば、子育て世代に表示されやすくなりますし、働き方改革について語れば労働環境やキャリアに関心を持つ人に届くかもしれません。こうした仕組みを活かせば、これまで直接つながることが難しかった層に対しても効率的にアプローチできます。
もし興味を持ってもらえれば、そこからフォロワーにつながり、さらに深く情報を調べてくれるきっかけにもなるでしょう。
制作コストと編集の負担を抑えられることもメリットの1つです。長尺の動画を撮影・編集しようとすると、機材や編集技術が必要になり、どうしても時間や費用がかかってしまいます。しかし、ショート動画ならスマートフォン1台あれば撮影から編集まで完結できます。
高性能な機材は必要ありませんし、難しい編集ソフトを使いこなす必要もありません。編集もシンプルで、無料のアプリやプラットフォーム内の機能を使えば、テロップや音楽を簡単に加えることが可能です。そのため、日々の活動風景やメッセージをスピーディーに発信でき、政治活動の合間にも無理なく取り入れることができます。
ショート動画は、広告費をかけずに広く発信できる点も大きなメリットです。従来なら広報紙や新聞広告、あるいはテレビCMなどに頼らざるを得ませんでしたが、これには相応の費用が必要でした。
その点、SNSのショート動画なら、プラットフォーム上でオーガニック(自然発生的)な拡散を狙うことができます。動画が面白かったり、共感を呼ぶ内容であれば、視聴者が自発的にシェアしてくれるため、広告費をかけずに多くの人々にメッセージを届けることが可能です。
実際に、アイデアと工夫次第では数十万回〜数百万回再生されることも珍しくなく、大きなバズを生み出せるかもしれません。
一度制作したショート動画は、YouTubeショート、TikTok、Instagramリールなど、複数のプラットフォームで使い回すことができます。各プラットフォームの特性に合わせて、BGMやハッシュタグを少し調整するだけで、異なるユーザー層に効果的にリーチすることが可能です。
こうした展開によって、動画制作の手間を最小限に抑えつつ、最大限の効果を狙えます。特に選挙期間のように時間やリソースが限られる状況でも、効率的な情報発信が実現できるでしょう。
ショート動画は、メインコンテンツへの導線としても活用できます。たとえば、短い動画で政策のポイントや活動のダイジェストを紹介し、「詳しくはフルバージョンのYouTube動画で」「続きは公式サイトへ」といった形で誘導すれば、自然にメインコンテンツに視聴者を引き込めます。
短い動画で興味を持った人は、「もっと知りたい」という気持ちになっている可能性が高く、そのタイミングで長尺動画やブログに触れてもらうことで、理念や政策をより深く理解してもらえます。
「ショート動画を活用した方がいいのは理解したけれど、実際にどうやって作ればいいのか分からない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。ここからは企画から投稿までの流れを以下の4つのステップに分けてご紹介していきます。
①動画内容の企画を立てる
②編集アプリを選ぶ
③スマートフォンなどで動画を撮影する
④動画を編集しテロップや音声を加えて投稿する
ショート動画を作るうえで、最初に行うのは「どんな内容にするか」という企画立てです。なんとなく撮影を始めるのではなく、目的やターゲットをしっかり意識して企画を固めることで、短い尺でも内容がブレずに伝わります。
企画を考える際のポイントは次のとおりです。
整理ができたら、テーマや大まかな流れを決め、簡単な台本や構成メモを作っておくと撮影や編集がスムーズに進みます。
企画が固まったら、次に動画を編集するためのアプリを選びます。ショート動画は短時間でテンポよく見せる必要があるため、最低限「カット編集(トリミング)」「テロップ挿入」「BGMや効果音の追加」ができる機能は欠かせません。
最近はスマートフォンだけで編集が完結するアプリが豊富にあり、初心者でも直感的に操作できるものが増えています。代表的なものには「CapCut」や「InShot」、そして各プラットフォームに備わっている編集機能などがあります。それぞれ使いやすさや機能面が異なるので、まずはいくつか試してみて、自分に合ったものを見つけましょう。
編集アプリが決まったら、いよいよ撮影に入ります。基本的にはスマートフォンのカメラで十分対応できますが、ビデオカメラの手ブレ補正やタイマー機能などを活用すると、より安定した映像が撮れます。撮影にあたっては、映像がブレたり音声が不鮮明になることもあるので、同じシーンを複数回撮っておくと安心でしょう。
できるだけ明るい場所を選び、雑音の入りにくい環境で撮影することも大切です。また、ズームを使用すると映像がブレやすくなるため、極力控えることをおすすめします。
撮影した素材は編集アプリに取り込み、不要な部分をカットしていきます。そのうえで、動画の内容をより分かりやすくするために、強調したいキーワードやセリフにテロップを加えましょう。特に、移動中は音声をオフにして視聴する人も多いため、テロップだけで内容が理解できるように工夫することが大切です。
さらに、動画の雰囲気に合ったBGMや効果音を追加すれば、リズミカルな映像に仕上がります。編集が完了したら、動画の内容に合ったハッシュタグをつけて、各プラットフォームに投稿しましょう。
ただ動画を投稿するだけでは、なかなか再生回数は伸びません。視聴者の心をつかみ、多くの人に見てもらうためには、いくつかの工夫が必要です。ここからは、ショート動画の再生回数を伸ばすためのポイントを6つご紹介します。
ショート動画の再生回数を伸ばすためには、まず「誰に向けて発信するのか」をはっきりさせることが大切です。たとえば「若年層」「地元の有権者」「無党派層」「特定の政策に関心を持つ人」など、できるだけ具体的にターゲットを定めておくことで、動画の内容に統一感が生まれます。
そのうえで、年齢や職業、視聴されやすい時間帯などを調べておくと、より効果的に企画を練ることができるでしょう。視聴者のニーズを理解すれば、どんな切り口が共感を呼ぶか見えてきますし、結果として再生回数アップにもつながります。
ショート動画は、2秒に1回のペースでカットを入れる のが理想的と言われるほど、テンポの速さが重要です。不要な間や無駄な言葉は徹底的にカットし、伝えたいメッセージを簡潔に、そしてリズミカルにまとめましょう。
視聴者は少しでも退屈だとすぐにスワイプしてしまうので、いかに飽きさせないかが重要になります。
ショート動画はスワイプ一つで次の動画へ移れるため、冒頭の3〜5秒が勝負どころです。冒頭で「この動画は面白そう」「自分にとって有益だ」と思ってもらえなければ、すぐに離脱されてしまいます。そこで効果的なのが、インパクトのあるシーンを最初に持ってくる方法です。
たとえば「皆さん、〇〇をご存じですか?」「〇〇問題、実は〇〇なんです」といった疑問や驚きを誘うフレーズを入れたり、派手な色使いや動きのある映像を入れたりすることで、目を止めてもらえる可能性が高まります。冒頭で関心をつかめれば、その後のメッセージも最後までしっかり届けられるでしょう。
ショート動画の再生回数を伸ばすためには、テーマ選びにも工夫が必要です。どれだけ編集が上手でも、専門的で難しい政策の話ばかりでは関心を持ってもらえません。大切なのは、視聴者が「自分事」として受け止めやすいテーマにすることです。
たとえば、「物価高で生活はどう変わる?」「子育て世代に役立つ制度」「「将来の年金は大丈夫?」など、日々の生活に直結する身近な話題や、誰もが共感できるテーマを扱うことで、「ちょっと見てみよう」と感じてもらいやすくなります。
このほか、「政治家ってこんなことにも関わっているんだ」という気づきを与えるような、意外性のあるテーマも効果的です。難しいことを難しいまま伝えるのではなく、親しみやすさを意識したテーマ設定で発信していきましょう。
ショート動画は、必ずしも音声ありで視聴されるとは限りません。通勤や通学の電車内、職場やカフェなど、音を出せない環境で見られることも多いため、テロップ(字幕)は必須です。特に、重要なメッセージやキーワードは、大きく分かりやすい文字で表示しましょう。
また、テロップに動きをつけたり、簡単なエフェクトを加えたりすることで視聴者の注意を引きやすくなります。なお、画面の端に文字を置くと、アプリのボタンやキャプションに隠れてしまうことがあるので配置には注意してください。
ショート動画は一過性の「バズ」を狙うというよりも、継続的に発信していくことが何より大切です。定期的に動画を投稿し続けることで、有権者に自然と顔や名前を覚えてもらう機会が増えますし、「この人は普段から有益な情報を発信している」という安心感や信頼感にもつながります。
最初のうちは再生回数が思うように伸びないかもしれませんが、地道に続けることで、必ず成果は見えてくるはずです。新しい支持層を広げるためにも、政治活動の一環としてショート動画の発信を習慣化していきましょう。
今回は、ショート動画の基本から作り方、再生回数を伸ばすためのポイントまでを解説してきました。ここ数年、SNS動画を積極的に活用した候補者が躍進する例も増えていますが、なかでもショート動画は若年層へのアプローチ手段として定着しつつあります。
ショート動画を活用するにあたって大切なのは、継続して発信し、少しずつ認知を積み重ねていくこと。工夫次第では大きな支持拡大につながる可能性もあるため、この機会にぜひショート動画を政治活動に取り入れ、新たな有権者との接点を築いてみてはいかがでしょうか。
【無料配布】誰でも容易に使える「ショート動画攻略マニュアル」※資料ダウンロード
{% module_block module...