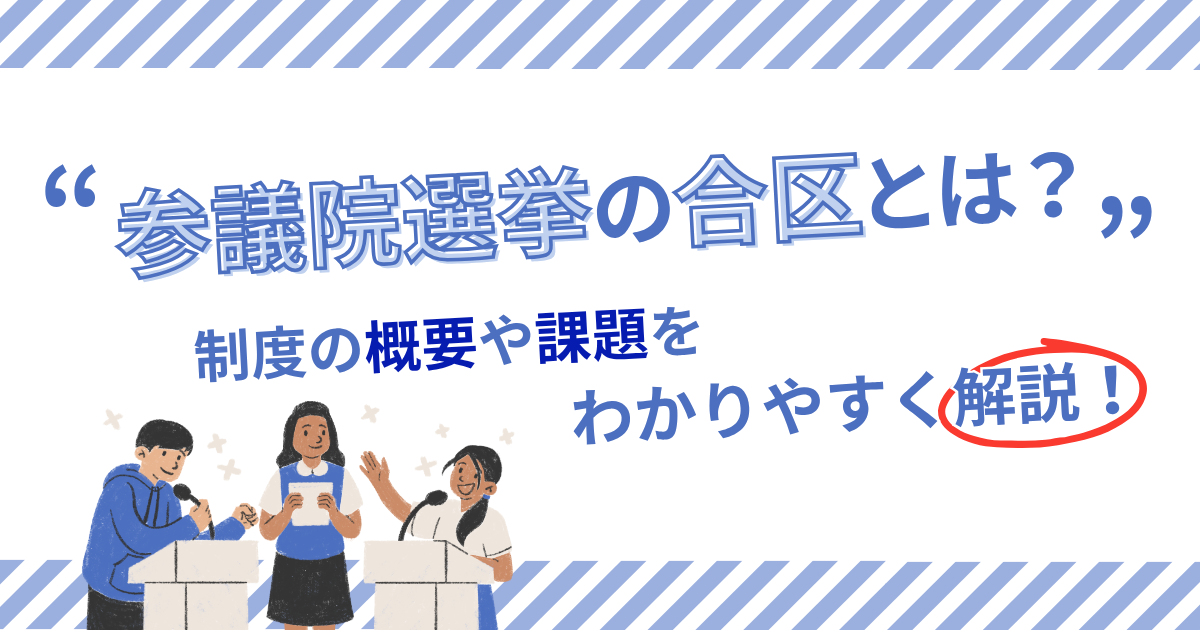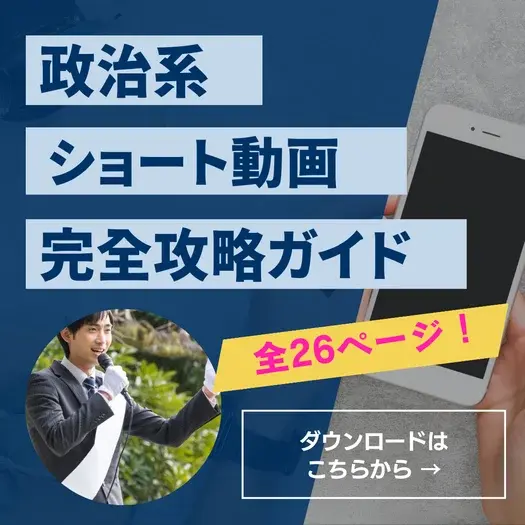はじめに
参議院選挙では、選挙区ごとに議席が割り当てられ、有権者が地域の代表を選ぶ仕組みが採用されています。しかし、人口の違いによって一票の価値に格差が生じることが課題となり、これを是正するために「合区(ごうく)」という制度が導入されています。合区は、複数の県を一つの選挙区とする仕組みで、これにより選挙の在り方が大きく変化しています。
本記事では、参議院選挙における合区制度の概要や対象地域、選挙活動への影響をわかりやすく解説します。候補者として知っておきたい実務上のポイントも整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
参議院選挙の合区とは
参議院選挙における合区とは、人口の少ない県同士を一つの選挙区としてまとめる仕組みです。具体的な内容や制度の背景を詳しく見ていきましょう。
特定枠制度とは?
ここで登場するのが2019年の参議院選挙から新たに加わった「特定枠」という制度です。以下でその仕組みや導入の背景、運用の詳細について、詳しく見ていきましょう。
参議院選挙の基本的な仕組み
合区の内容を理解するために、まずは参議院選挙全体の基本構造を押さえておきましょう。
参議院選挙は、選挙区選出議員と比例代表選出議員を組み合わせた制度です。選挙区選出は、都道府県ごとに定められた選挙区で行われ、有権者は地域の候補者に一票を投じます。
比例代表選出では、全国を一つの単位とし、政党ごとに投票する仕組みです。任期は6年で、3年ごとに半数が改選されるため、継続的に民意を反映できる体制となっています。選挙区と比例代表の両面から国民の意見を国政に反映させることが基本です。
合区とは
合区とは、人口の少ない県同士を一つの選挙区として統合する制度です。これにより、各選挙区でできるだけ一票の価値の差を縮めようという狙いがあります。
日本の参議院は、憲法で「全国民の代表」と位置づけられていますが、かつては人口規模に関わらず、各県にほぼ均等に議席が割り振られていました。その結果、都市部と地方で著しい「一票の格差」が生じ、最高裁から違憲状態と指摘される事態に至りました。
こうした背景を受けて、2016年の選挙から合区が導入され、特に著しく人口が少ない選挙区については、他県と統合する形が取られています。これにより法的な均衡は一定程度保たれたものの、地域の声が届きにくくなるという新たな課題も生まれています。
合区の対象になった選挙区
2016年の参議院選挙で初めて「合区」となったのが、「鳥取・島根」と「徳島・高知」の二つの選挙区です。いずれも、それまでは鳥取、島根、徳島、高知の各県が独立した小選挙区で、改選ごとの定数1名とされていました。
しかし、合区によって隣接する県同士が統合され、合計4議席に再編されました。これにより格差是正が一定程度進み、一票の格差も法的に合憲と認められる水準まで縮小しました。特に都市部と地方の投票価値の偏りも改善されています。
合区は、制度上「小さな選挙区をまとめることで票の重みを均衡させる」という意味で、選挙制度の公平性を保つ重要な一手となりました。
一票の格差の問題
「一票の格差」とは、有権者一人あたりの投票価値が、地域によって大きく異なる状態を指します。人口の少ない地方では、一票の重みが都市部に比べて過剰に高くなり、結果として有権者の平等が損なわれる事態が生じます。
具体例で考えてみましょう。たとえば、議員定数1の選挙区Aで有権者が80万人、選挙区Bで有権者が20万人の場合、同じ1議席でも、選挙区Aの有権者の一票の価値は、選挙区Bの4分の1にしかなりません。つまり、選挙区Bの有権者は、実質的にAの有権者の4倍の影響力を持つ計算になります。
こうした格差は、特に人口が集中する都市部で一票が軽くなり、人口が少ない地方で一票が重くなる傾向が顕著です。選挙制度の公平性を確保するためには、この格差の是正が常に求められています。
合区導入による変化
合区の導入は、選挙制度の仕組みや地域の政治状況にさまざまな変化をもたらしました。ここからは具体的な影響について見ていきましょう。
一票の格差の改善
合区の導入によって、一票の格差は以前に比べて着実に縮小しました。
たとえば、2010年の参議院選挙では選挙区間の最大格差は5.00倍、2013年も4.77倍という非常に大きな開きがあり、いずれも最高裁から「違憲状態」との厳しい指摘を受けていました。しかし、合区を初めて適用した2016年の参議院選挙では、この格差は3.08倍にまで縮小。依然として「完全な平等」とは言えませんが、最高裁はこの水準について「合憲」との判断を下し、一定の是正効果を認めました。
こうした結果からも、合区の実施は、憲法上求められる投票価値の平等に向けた選挙制度の見直しとして一定の成果を上げたと評価できます。
比例代表に特定枠を導入
合区によって生じた地域代表の不足を補うため、比例代表に「特定枠」と呼ばれる救済措置が新たに導入されました。この「特定枠」とはどのような制度なのか、以下で解説します。
特定枠とは
特定枠とは、比例代表の中で政党が優先的に当選させたい候補者を名簿の上位にあらかじめ指定できる仕組みで、部分的に「拘束名簿式」を取り入れた新制度です。通常の比例代表では、有権者が候補者の個人名を記入し、得票数の多い順に当選者が決まりますが、特定枠に登録された候補者は個人票に関係なく、政党が獲得した議席から優先的に配分されます。
この仕組みにより、選挙戦で個人名票を集めにくい候補や、地域的に選挙区が消滅した候補を確実に当選させることが可能になりました。ちなみに、この特定枠を使用するかどうかは政党の自由で、義務ではありません。
2019年の参議院選挙で初めて導入された際は、3つの政党・政治団体が合わせて5人の候補者が特定枠で立候補し、そのうち4人が実際に当選を果たしました。
合区対象県の救済策としての特定枠
特定枠の導入は、合区によって代表を送り出しにくくなった県の「救済策」として重要な役割を担っています。たとえば、徳島県や鳥取県といった、合区により独自の選挙区を失った県では、「自分たちの代表者を確保できないのではないか(=県の声が国政に届きにくくなるのではないか)」という強い懸念が生まれました。
こうした声に応えるため、比例代表において特定枠が新設され、政党が合区対象県の候補者を名簿上位にあらかじめ登録できる仕組みが設けられたのです。これにより、有権者が個人名で票を入れなくても、政党の獲得議席に応じて、その地域の候補者が優先的に当選できる道が開かれました。
定数減に伴う他選挙区での定数増
合区の導入により、小規模県の議員定数は減少しましたが、参議院全体の議席数は一定数を維持する必要があります。
では、合区によって減った議席はどのように調整されるのでしょうか。
実は、減った定数は別の選挙区で増やすことで全体の議席数を保っています。合区設置が決定された2015年の公職選挙法改正当時、参議院選挙区の総議席数は146でした。この議席数に合わせて、合区によって削減された4議席分を、人口の多い都市部を中心に配分し直したのです。
具体的には、東京選挙区や愛知選挙区、兵庫選挙区など、一票の価値が軽くなりがちな大規模選挙区で定数を増やし、投票価値の不均衡を調整しました。この定数見直しは、単に合区による定数減を補うためだけではなく、全国の選挙区間でできる限り投票価値の差を縮めることを目的として、複数の選挙区で広く定数が再配分されました。
このように、議席配分は一部の県だけでなく、日本全体の選挙制度を公平に整えるために、細かく設計されています。
合区で直面する選挙活動の課題
合区は「一票の格差」の是正に一定の効果をもたらしましたが、その一方で、現場では合区を見直すべきだという声も根強く存在します。
なぜ今、合区に対して再考を求める声が上がっているのか。ここからは、合区によって生まれた4つの選挙運動上の課題を具体的に見ていきましょう。
有権者との接点不足による投票率低下
合区が導入された後、選挙区が広くなり、候補者が有権者一人ひとりと直接接する機会が減少しました。その影響が特に表れたのが、2019年の参議院選挙です。この選挙では、徳島県の投票率が全国で最も低い38.59%を記録し、鳥取・島根・徳島の3県でいずれも過去最低の投票率となりました。
合区によって、有権者が「自分の声が届きにくい」「候補者が遠い存在になった」と感じやすくなり、選挙への関心が薄れてしまったことが一因と考えられています。こうした状況に対し、中国地方知事会など地方自治体も「合区が地域の政治参加意欲を低下させている」として、選挙制度の見直しを求める意見書を提出する動きが見られました。
合区は票の平等を目指した仕組みですが、有権者との距離が広がることで新たな課題を生んでいるのです。
県境をまたぐ代表選出の難しさ
合区では隣接する複数県から一人の代表を選ぶことになりますが、これが選挙区内の「地域間競争」を激化させるという課題もあります。
たとえば、鳥取・島根選挙区の場合、鳥取県の候補者と島根県の候補者が票を奪い合う構造が常態化し、どちらの県から代表を送り出すかが県民にとって大きな関心事になっています。この結果、地域ごとに「自分たちの代表」を確保したいという強い思いが生まれ、県境をまたぐ選挙区での合意形成が非常に難しくなります。
ときに地域対立の構図が強まることで、選挙戦が本来目指すべき政策論争よりも、出身地の争いに終始してしまうケースも少なくありません。
広域選挙区における選挙運動の負担
合区により選挙区が広域化したことで、候補者が選挙運動で移動しなければならない範囲が大幅に拡大しました。
たとえば、鳥取・島根選挙区は東西で300km以上に及び、徳島・高知も広い山間部を含む長距離移動が必要です。このため、候補者にとっては地理的・時間的負担が非常に大きくなり、限られた期間で全地域をくまなく回ることは現実的に困難です。
特に少人数で活動する無所属候補や新人にとっては、大都市選挙区以上に厳しい環境と言えます。広い選挙区でどこに重点を置いて活動するかという戦略も難しく、選挙運動の公平性確保が課題になっています。
主務県制度に伴う選挙運営上の配慮
合区では、実務上の選挙管理も煩雑になります。そのため、合区対象選挙区には「主務県制度」が導入され、選挙の中心的な事務処理は一方の県が担当する仕組みが採用されました。たとえば、徳島・高知選挙区では、徳島県が主務県として、選挙公報の作成や当選人の確定事務を担っています。これは選挙運営を効率化するために必要な措置ですが、
一方で、選挙結果の集計や広報活動が主務県に偏ることへの公平性の配慮も求められます。投票所の設置や公報の配布など、選挙の基盤に地域差を生じさせないよう、選挙管理委員会には高い調整力と丁寧な運営が期待されています。これは選挙運営を効率化するために必要な措置ですが、一方で、選挙結果の集計や広報活動が主務県に偏ることへの公平性の配慮も求められます。投票所の設置や公報の配布など、選挙の基盤に地域差を生じさせないよう、選挙管理委員会には高い調整力と丁寧な運営が期待されています。
合区をめぐる近年の動向
合区制度は導入以降も議論が続いており、近年の選挙や裁判でその意義や課題が改めて問われています。ここでは、合区に関連する最新の動きについて確認していきます。
2022年参議院選挙における格差の憲法判断
2022年7月に実施された参議院選挙では、最大で3.03倍の一票の格差が生じました。この格差について複数の弁護士グループが、「投票価値の平等を保障した憲法に違反する」として選挙の無効を求める訴訟を全国で提起。各地の高等裁判所は選挙無効を認めませんでしたが、憲法判断は裁判所ごとに意見が分かれました。
最終的に2023年10月、最高裁判所大法廷は「合区の導入などを通じて格差は一定程度縮小しており、現状は拡大傾向にもない」と判断し、憲法違反には当たらないとの結論を示しました。一方で、15人の裁判官のうち1人は「違憲であり選挙は無効」と主張し、さらに2人が「違憲状態」とする意見を述べるなど、完全な一致には至りませんでした。
裁判所は立法府に対し、選挙制度全体の構造的見直しも含め、格差是正に向けた継続的な検討を求めています。
2025年参議院選挙における合区の継続方針
2025年夏に予定されている参議院選挙について、自民党は徳島・高知、鳥取・島根の合区を継続する方針を固めました。党本部は2023年12月、対象となる各県連の幹部に「合区解消は見送る」と正式に伝え、これを受けて合区を前提とした選挙準備が進められてきました。特定枠についても、これまでと同様に設ける方向で調整が進められ、候補者が擁立しにくい県を比例代表で支援する仕組みは今回も引き継がれる見通しです。
県連レベルではすでに候補者選定が進んでおり、2025年6月には徳島・高知両県連が協議を行ったことが報じられています。朝日新聞によれば、6月18日時点で徳島・高知合区では、自民党や無所属を含む複数の候補者が届け出を済ませており、現職無所属と自民・参政党・NHK党が競い合う構造になっています。
このように、合区を前提とした選挙戦はすでに事実上始まっており、地域代表をどう確保するのか、そして特定枠がどのように活用されるのかが、今後の選挙戦の注目点となりそうです。
候補者・政治家のための合区に関するQ&A
ここでは、立候補や選挙活動において実際に直面しやすい疑問について、具体的に解説していきます。
合区の場合、立候補の届け出はどこでできますか?
合区では複数の県をひとつの選挙区として扱いますが、立候補の届け出は選挙区ごとに指定された「主務県」の選挙管理委員会で行うことになります。
たとえば、徳島・高知選挙区の場合、徳島県が主務県に指定されており、候補者は徳島県選挙管理委員会に必要書類を提出することになります。主務県制度は、合区で生じる事務負担を一本化するために設けられたルールで、もう一方の県で届け出を行うことはできません。候補者はあらかじめ主務県を確認し、手続きに誤りがないよう注意が必要です。
選挙カーや事務所はどう運用すればいいですか?
合区では選挙区が広くなることを踏まえ、選挙事務所や選挙カーの運用に特例が設けられています。通常、候補者1人につき選挙事務所は1カ所までとされていますが、合区では特例で2カ所まで設置が可能です。ただし、「1県に1カ所」などの規定はなく、どの場所に事務所を置くかは候補者が自由に判断できます。
選挙カーも本来1台までですが、合区の場合は2台まで使用が認められ、選挙運動の機動力を確保できます。さらに、選挙運動員が無料で電車やバスに乗れる「特殊乗車券」は30枚に増え、地方紙が複数にまたがる合区を考慮し、新聞広告の掲載回数も通常の5回から10回に拡充されています。
広い選挙区で効率的に有権者にアプローチするにはどうしたらいいですか?
合区選挙は物理的な広さが最大の課題です。効率的に有権者にアプローチするためには、戦略的に「重点地域」を設定し、すべてを均等に回ろうとせず、支持を伸ばせる地域を見極めて集中的に活動することが重要です。特に人口が多い都市部と、地域密着の票が見込める地元基盤を軸に、メリハリをつけた行動計画を立てるべきでしょう。
また、選挙カーのルート選定、SNSを活用した情報発信、地元メディアとの連携も不可欠です。SNSは広域選挙で特に威力を発揮し、県境を超えた支持拡大には効果的な手段です。
まとめ
本記事では、参議院選挙における合区制度の仕組みや背景、実務上の影響について詳しく解説しました。
合区は、一票の格差を是正する目的で導入された制度ですが、候補者や有権者にとって新たな課題も生じています。広域にまたがる選挙区での活動や、有権者との接点確保は、今後も重要な検討事項となるでしょう。合区の仕組みを正しく理解し、最新の動向を把握することが、適切な選挙戦略の構築につながります。
「私たちの当選・再選GO!は、政治家・選挙立候補者の方へ向けweb制作・選挙、政治活動用の動画制作、名刺デザイン等を行っており、あなたの挑戦をトータルでサポートします。」
「ご相談は無料です。あなたの志を、現実の力に変えるために。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。」