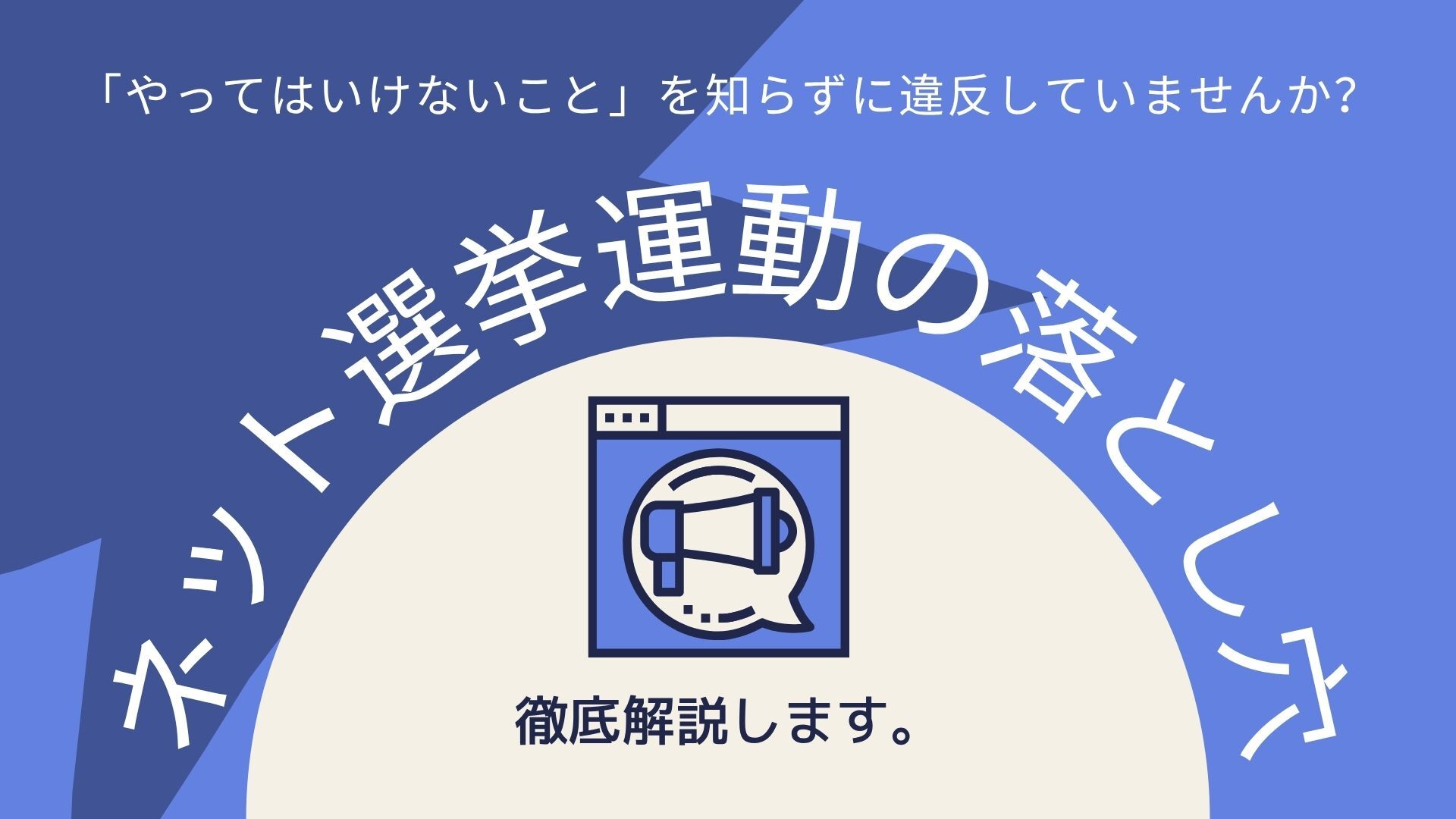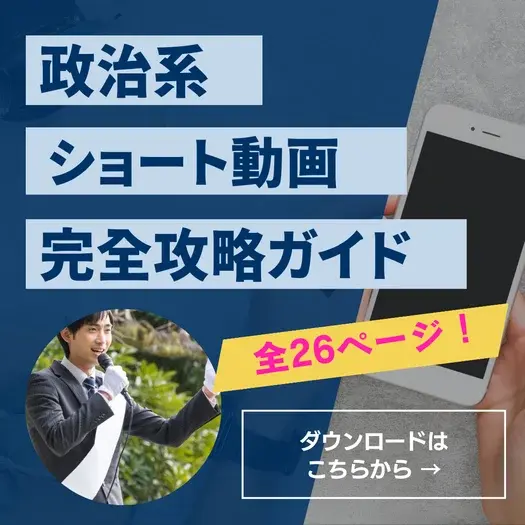はじめに
選挙カーからの連呼、駅前でのビラ配り、そしてポスター掲示。
長らく、日本の選挙活動はこれらの「アナログ」な手法が中心でした。しかし、2013年の「ネット選挙運動」解禁により、選挙の風景は一変します。X(旧Twitter)が「情報戦と論戦の場」として定着する一方、ここ数年で、それ以上に急速な勢いで選挙戦略の「主戦場」となりつつあるのが「Instagram(インスタグラム)」です。
なぜなら、インスタは従来の選挙手法では届かなかった「若年層」や「政治的無関心層」に、候補者の「人柄」や「熱意」をビジュアルで直感的に伝える最強のツールだからです。しかし、このインスタ戦略には、重大な「落とし穴」が潜んでいます。それは、インスタの持つ「気軽さ」や「日常感」ゆえに、候補者本人や陣営、さらには熱心な支援者(一般人)までもが、悪意なく「うっかり」と公職選挙法(こうしょくせんきょほう)に違反してしまうリスクが非常に高い、という事実です。
「公職選挙法」という法律は非常に古く、複雑で、現代のSNSの機能に完全に対応しきれていません。
「知らなかった」「うっかりだった」「良かれと思ってやった」
こうした言い訳は、選挙管理委員会や警察には一切通用しません。たった一つの「うっかり投稿」が、警告、投稿削除命令、最悪の場合は「当選無効」や「逮捕」といった、取り返しのつかない事態を招く可能性があるのです。
この記事では、選挙ブログを運営する私たちだからこそお伝えしたい、「インスタ選挙戦略」において絶対に避けるべき「NGな選挙違反リスト」を、具体的な事例と共に約6,000文字で徹底的に解説します。「攻め」の戦略と同時に「守り」の知識を万全にし、クリーンで効果的なネット選挙を実現しましょう。
目次
第1章:「うっかり違反」の温床。なぜインスタは危険なのか?
なぜ、他のSNSと比べても、インスタは「うっかり違反」の温床になりやすいのでしょうか。それは、インスタのプラットフォームが持つ「3つの特性」に起因しています。
ストーリーズ(24時間)の「気軽さ」の罠
24時間で消える「ストーリーズ」は、候補者の「素顔」や「舞台裏」を発信するのに最適な機能です。しかし、その「気軽さ」と「即時性」が仇となります。例えば、選挙運動が禁止されている「期間外」に、つい「〇〇選挙、頑張ります!投票お願いします!」といった投稿を気軽にあげてしまう。この「うっかり」が、公選法で厳しく禁じられている「事前運動(じぜんうんどう)」に直結します。
リール(短尺動画)の「拡散力」の罠
リールは、フォロワー以外にも爆発的に拡散する(バズる)可能性がある、インスタ最強の機能です。しかし、その拡散力ゆえに、一度「違反」となる内容(例:相手候補への誹謗中傷、事実誤認)を投稿してしまうと、瞬く間に広がり、候補者本人の手では削除・訂正が追いつかなくなります。「バズった」結果が「炎上」や「公選法違反の証拠拡散」になるリスクをはらんでいます。
支援者の「善意」の罠
インスタは「共感」のSNSです。候補者の投稿に感銘を受けた支援者(一般の有権者)が、「この人を応援したい!」という純粋な善意で行動を起こしやすいプラットフォームです。しかし、法律を知らない支援者が、うっかりDMで投票依頼を広めたり、自費で応援広告(プロモーション)を出そうとしたりすることで、支援者自身が「選挙違反」の当事者になってしまうケースが懸念されます。
第2章:すべての基本 。「政治活動」と「選挙運動」の鉄の境界線
インスタ戦略における違反の9割は、この「境界線」の誤解から生じます。公職選挙法は、政治家(や支援者)の活動を「政治活動」と「選挙運動」の2つに厳格に分類しています。
政治活動
●内容:
自身の政策や理念、政治信条を訴えること。
党勢を拡大するための活動(例:「〇〇党は子育て支援に力を入れています」)。
時事問題に対する見解を述べること。
活動報告(例:「今日は〇〇を視察しました」)。
●ルール:
原則として、いつでも、誰でも、自由にできます。
●インスタでの例:
「〇〇区の待機児童問題について、私はこう考えます。」(フィード投稿)
「今日は地域の清掃活動に参加しました!」(ストーリーズ)
「日本の未来には教育投資が必要です。」(リール)
選挙運動
●内容:
「特定の選挙」において、
「特定の候補者(または政党)」に、
「当選させる(または落選させる)こと」を「目的」として行う、投票の勧誘や働きかけ。
●例:
「〇〇区議会議員選挙、私〇〇太郎に、あなたの一票を!」
「A候補を当選させてください!」
「B候補だけは落選させよう!」
●ルール:
「選挙運動期間中」しか行うことができません。
選挙運動期間とは、「公示日(告示日)の立候補届出後 ~ 投票日の前日(23:59)まで」です。
この境界線こそが、インスタ戦略で「うっかり違反」をしないための生命線です。
第3章:【インスタ選挙違反NGリスト】7つの致命的な落とし穴
それでは、インスタを使ったネット選挙戦略で、具体的に「何が」「なぜ」NG(選挙違反)になるのかを、リスト形式で徹底解説します。
期間の違反
1、選挙期間「外」での投票依頼(事前運動)
●違反内容:
選挙運動期間(公示日~投票日前日)以外の時期に、特定の選挙に関する「投票依頼(選挙運動)」を行うこと。
●公選法のルール:
公職選挙法第129条(選挙運動の期間)
●インスタでの「うっかり」例:
立候補表明の記者会見の様子を、公示日の1ヶ月前にインスタのフィードに投稿し、「〇〇選挙、全力で戦います!皆様の清き一票をお願いします!」とキャプションに書いてしまう。
まだ公示日前なのに、プロフィールの自己紹介文に「〇〇選挙に立候補予定。私に投票してください!」と記載してしまう。(※プロフィール欄も「常時表示される文書図画」とみなされ、違反となります)
ストーリーズの「質問箱」で、「次の選挙、頑張ってください!」という応援コメントに対し、「ありがとうございます!ぜひ私に一票を!」と返信・公開してしまう。
●なぜNGか?:
法律で定められた期間外に選挙運動を許すと、お金や時間がある人(現職など)だけが有利になり、選挙の「フライングスタート」が横行し、公正な選挙が担保できないためです。
●安全な戦略(OKな例):
選挙期間外は、徹底して「政治活動」に留めます。
「〇〇選挙への立候補を決意しました。私の政策は〇〇です。全力で活動します!」
(※投票依頼がないからOK)
「〇〇区の未来のために、私は働きます!」
(※投票依頼がないからOK)
2、「投票日当日」の更新(当日運動)
●違反内容:
投票日当日(0時00分 ~ 投票所の閉鎖時刻まで)に、選挙運動(投票依頼)を行うこと。
●公選法のルール:
公職選挙法第129条(選挙運動の期間)
●インスタでの「うっかり」例:
投票日当日の朝、「おはようございます!本日、投票日です。最後の最後まで、私〇〇太郎をよろしくお願いします!」とストーリーズやリールを投稿する。投票日前日の夜に投稿した「最後のお願い!」というフィード投稿を、投票日当日にストーリーズで「再共有(リポスト)」する。
支援者が「〇〇さんに投票してきました!皆さんもぜひ!」と、投票先を明記して投稿する。(※これは「選挙運動」とみなされる可能性が極めて高い、危険な行為です)
●なぜNGか?:
投票日当日は、有権者が静かな環境で冷静に最後の一票を判断するための「沈黙の期間」とされているためです。
●安全な戦略:
特定の候補者名や政党名を出さずに、「投票啓発(とうひょうけいはつ)」を行うことは合法です。
「今日は〇〇選挙の投票日です。日本の未来のために、皆さん投票に行きましょう」
「投票完了しました!大切な一票、投じてきました。」
方法の違反
3、有料広告(プロモーション)の利用
●違反内容:
選挙運動の目的で、有料のインターネット広告(SNS広告含む)を利用すること。
●公選法のルール:
公職選挙法第142条の3
(インターネット等を利用する方法による選挙運動)
●インスタでの「うっかり」例:
選挙運動期間中に投稿した「渾身のリール動画(政策解説)」が好評だったため、インスタの「投稿を宣伝(Boost Post)」ボタンを押し、お金を払って〇〇区の30代女性にターゲットを絞って広告配信してしまう。
熱心な支援者が、「A候補を当選させたい!」という善意で、自分のお金を使ってA候補の応援投稿をインスタで有料広告として出してしまう。(※支援者による有料広告も「買収罪」に問われるリスクがあり、絶対にNGです)
●なぜNGか?:
「お金のある候補者(政党)」だけが、広告の力で情報を大量に拡散でき、選挙の公正と公平が著しく害されるためです。
●安全な戦略(OKな例):
ネット選挙戦略は、すべて「オーガニック(無料)」で行うのが鉄則です。拡散力は、広告費ではなく「コンテンツの質(共感性・有益性)」で稼ぎます。
4、DM(ダイレクトメッセージ)での投票依頼
●違反内容:
DM(ダイレクトメッセージ)機能を使って、有権者に個別に「投票依頼」のメッセージを送ること。
●公選法のルール:
公選法では、「電子メール(Eメール)」による選挙運動を厳しく制限しています(候補者・政党が、事前に承諾を得た相手に「メルマガ」として送る場合などを除く)。
インスタのDMやLINEの個人チャットは、公開されたSNS投稿とは異なり、この「電子メール」と同等(閉鎖的な通信)と見なされる可能性が極めて高いです。
●インスタでの「うっかり」例:
候補者本人や陣営スタッフが、インスタのフォロワーに対し、一件一件DMで「〇〇です。いつも応援ありがとうございます。ぜひ私に一票をお願いします」と送信する。
支援者が、自分の友だちリスト(フォロワー)に、DMで「A候補をよろしく!」と一斉送信する。
●なぜNGか?:
公開されていない場所での投票依頼は、有権者にとって「断りにくい」という心理的圧力を生む可能性や、なりすましによる誹謗中傷に使われるリスクがあるためです。
●安全な戦略(OKな例):
選挙運動(投票依頼)は、必ず「公開」された場所(フィード投稿、ストーリーズ、リール、インスタライブ)で行います。DMは、有権者からの「意見・相談」を「受ける(受信する)」窓口としてのみ活用し、陣営から「投票依頼」を「送る(送信する)」ことには絶対に使わない、というルールを徹底します。
内容の違反
5、虚偽事項公表(デマ・ウソ)
●違反内容:
当選させる目的、または落選させる目的で、候補者の経歴、素行、所属政党などに関して「ウソ(虚偽の事実)」を投稿すること。
●公選法のルール:
公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)
●インスタでの「うっかり」例:
相手候補を落選させるため、「A候補には逮捕歴があるらしい」「B候補は〇〇というカルト宗教の信者だ」といった、事実無根のデマを画像付きでフィード投稿する。
相手候補の演説動画の一部だけを悪意を持って切り抜き、「C候補は『増税する』と公言した!」などと、本来の文脈とは異なる(事実をゆがめた)リール動画を作成・投稿する。
●なぜNGか?:
デマやウソは、有権者の「正しい判断」を妨げる最たるものであり、選挙の公正を根本から破壊する重罪です。
●安全な戦略(OKな例):
他候補の批判(政策批判)は、必ず「事実(ファクト)」と「公式な情報源(ソース)」に基づいて行います。SNS戦略は、ネガティブ・キャンペーン(相手を下げる)よりも、ポジティブ・キャンペーン(自分を上げる)に徹する方が、インスタの「共感」の文化と相性が良く、結果的に支持が広がりやすくなります。
6、買収(ばいしゅう)の疑い
●違反内容:
選挙運動に関して、有権者に対し金銭や物品を提供したり、利益を供与する約束をしたりすること。
●公選法のルール:
公職選挙法第221条(買収及び利害誘導罪)
●インスタでの「うっかり」例:
選挙運動期間中に、インスタでキャンペーンを企画し、「私のこの投稿(リール)をストーリーズでシェアしてくれた人の中から、抽選で10名にAmazonギフト券をプレゼント! #〇〇太郎を当選させよう」と投稿する。支援者の飲食店が、「〇〇太郎さんに投票したと(投票済証などで)証明してくれたら、ドリンク1杯無料サービス!」とインスタで宣伝する。
●なぜNGか?:
これは「投票」という神聖な権利を「金品」で買う行為であり、民主主義の根幹をなす「買収」そのものです。
●安全な戦略(OKな例):
選挙と「金品(プレゼント企画)」を紐づけることは、いかなる理由があっても絶対に禁止です。有権者に依頼できるのは「投票」という無形の行動支援のみです。
主体の違反
7、18歳未満(未成年者)による選挙運動
●違反内容:
18歳未満の者(未成年者)が、選挙運動を行うこと。
●公選法のルール:
公職選挙法第137条の2(選挙運動の禁止)
●インスタでの「うっかり」例:
17歳の高校生が、自分のインスタアカウントで「私はA候補を応援します!皆さん、Aさんに投票しましょう!」とストーリーズやフィードに投稿する。候補者本人が、自分の16歳の子供に「お父さん(お母さん)の応援投稿をして」と頼み、子供が自分のアカウントで投票を呼びかける。
陣営が、18歳未満の学生ボランティアに「インスタの運用(投稿作業)」を任せてしまい、その学生が(候補者の指示として)投票依頼の投稿を作成・アップロードする。
●なぜNGか?:
学業を優先すべき未成年者を、選挙という政治活動から保護するため、とされています。
●安全な戦略(OKな例):
18歳未満の者が、「選挙運動」ではなく「政治活動(政治的意見の表明)」を行うことは、禁止されていません。(例:「〇〇党の政策が好きだ」「政治についてこう思う」)陣営としては、この「境界線」を18歳未満の支援者に教えるのは困難を極めるため、「18歳未満の人は、特定の候補者名や政党名を出した『投票依頼』は絶対にしないでください」と明確にアナウンスし、予防線を張るべきです。
第4章:「うっかり違反」を防ぐための「守り」の体制づくり
これらの「NGリスト」は、候補者や陣営スタッフが「知っている」だけでは防げません。「うっかり」は、多忙な選挙期間中にこそ起こります。違反を防ぐためには、「仕組み(ルール)」で守るしかありません。
「投稿マニュアル」を必ず作成する
「平時(政治活動)」と「選挙運動期間中」で、使ってよい言葉、NGな言葉を明確にリスト化します。「事前運動」「当日運動」「DMでの投票依頼」といったNGの重要ルールを、マニュアルの冒頭に赤字で記載します。
「法務・コンプライアンス担当者」を必ず置く
SNSを運用するチーム(特に若いスタッフ)とは別に、公選法に詳しいベテランスタッフや、可能であれば弁護士などの専門家を「法務チェック担当」として置きます。選挙運動期間中の投稿は、必ずこの担当者が「投稿前に」法的なチェック(ダブルチェック)を行うフローを義務化します。
「支援者(一般人)」への周知・教育を徹底する
違反は、善意の支援者が起こすことが多々あります。公式HPやインスタ投稿で、「支援者の皆様へのお願い(公選法上の注意)」というページ(投稿)を必ず作成・公開します。「DMでの投票依頼はNGです」「有料広告は絶対にやめてください」「18歳未満の方は投票依頼できません」といった、支援者がやりがちな「うっかり違反」を、あらかじめ周知徹底することが、陣営の最大のリスク管理となります。
まとめ
インスタグラムは、候補者の「人柄」と「熱意」をビジュアルで伝え、政治的無関心層の「共感」を呼び起こす、現代の選挙戦略において最強の武器の一つです。しかし、その武器は、公職選挙法という「安全装置」を理解せずに使えば、候補者自身や大切な支援者を傷つける「凶器」にもなり得ます。「うっかり」では済まされないのが、選挙違反の恐ろしさです。
7つのNGリスト
- 事前運動(選挙期間外の投票依頼)
- 当日運動(投票日当日の投票依頼)
- 有料広告(「投稿を宣伝」ボタン)
- DM(閉鎖空間での投票依頼)
- 虚偽事項(デマ、ウソ、悪意ある切り抜き)
- 買収(プレゼント企画との連動)
- 18歳未満(未成年者による選挙運動)
これらの「境界線」を明確に理解し、チーム全体で「守り」の体制を固めること。それこそが、インスタという主戦場を制し、クリーンな選挙戦略を成功させるための、最低限かつ最重要の「常識」なのです。